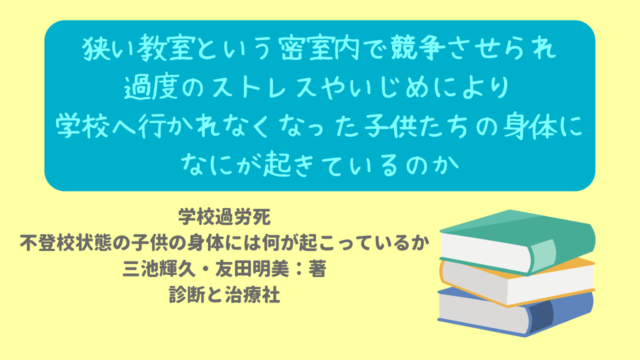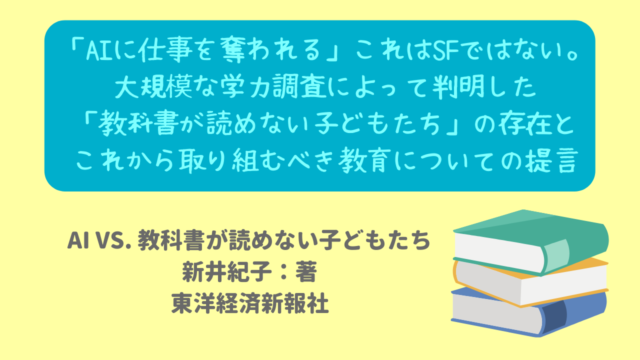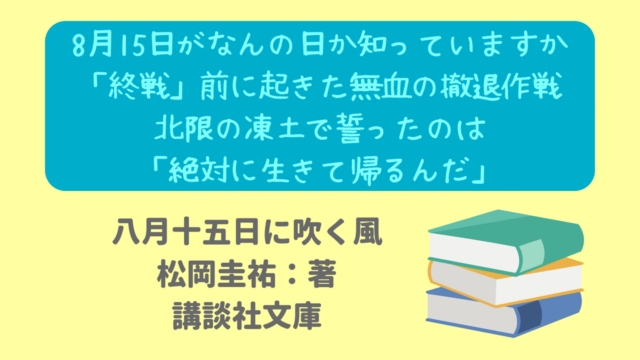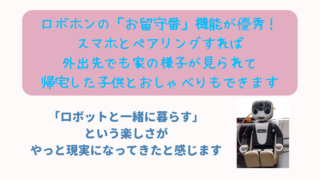吃音 伝えられないもどかしさ
近藤雄生:著
新潮社
あらすじ
自身も吃音だった著者が、吃音に悩み苦しむ人々に会い、取材を重ねたルポルタージュ。
NHK Eテレの「バリバラ」という番組に出演した吃音者・高橋に取材を申し込んだことから著者の吃音と向き合う旅が始まる。
吃音が原因で人生が左右された様々な人の姿を追い、彼らがどのように吃音と向き合い、乗り越えていくのかを伝えていく。
徹底的な訓練で流暢な話し方を手に入れた人、その訓練法の開発に人生をかける人、そして乗り越えることができず死を選んだ人。
「うまく話せない」というだけではない、吃音という苦しみの深さを実感として読み取ることができる、当事者の現実をていねいに描いたノンフィクション。
ニャム評
『吃音〜伝えられないもどかしさ』(新潮社)刊行記念
「『吃音』について著者、近藤雄生が語る~聞き手・重松清」
出演:近藤雄生(ライター)、重松清(作家)
日時:2019.05.31(FRI)20:00~22:00(19:30開場)
場所:本屋B&B(@book_and_beer)
東京都世田谷区北沢2-5-2 ビッグベンB1F
入場料:前売1,500yen + 1drink
当日店頭2,000yen + 1drink
著者の近藤さんは「遊牧夫婦」シリーズなどを記したノンフィクション作家です。
個人的には「オオカミと野生のイヌ」がとっても気になっています。
おもしろそう・・・!
近藤さん(@ykoncanberra)は大学院修了後、奥さんと一緒に世界を旅しながら各地でルポルタージュや写真を情報誌などに寄稿し、現在は作家として活躍されています。
大学院を修了した彼がなぜ日本で就職せず、世界を旅することを選択したのかというと、吃音があるためでした。
電話での応答ができない、重要な場面でうまく話せないということに悩み、一般的な就職は諦め、世界へ出て文章を書く仕事ができないかと考えたそうです。
そして、「職業としての文章家」を目指すにあたり、向き合うべきテーマとして選んだのが「吃音」でした。
吃音とは、発話が流暢にできない症状を指します。
「ぼ、ぼ、ぼくは」というように、ひとつの文字が連続して出てしまったり、頭に思い浮かんでいる言葉がどうしても言葉として出せないなどの症状です。
100人にひとりはいるという統計もあり、マリリン・モンローもそうであったといいます。
詳しくは「国立障害者リハビリテーションセンター研究所」のホームページで詳しく解説しています(最終更新日が古いのがやや気になりますが)。
吃音について
感覚機能系障害研究部
国立障害者リハビリテーションセンター研究所
近藤さんは「バリバラ」というテレビ番組に出演していた吃音者・高橋さんへ取材を申し込み、彼の人生を追い始めます。
高橋さんは吃音に深く悩み、18歳のときに飛び降り自殺します。
ところが一命をとりとめ、自死はかないませんでした。
死ぬことができなかった高橋さんは、その後も就職や家庭の事情など大きな苦労を背負いつつも、大切な娘を育てなければという責務にかられて必死に生きていきます。
そんななか、やはり吃音に苦しんだ末に言語聴覚士の道を選択したという羽佐田さんが、「バリバラ」を見て高橋さんの吃音改善を支援することになります。
吃音は研究が足りず未知のことが多い障害で、話し方の訓練などで改善は期待できますが、「完全に治る」というのは難しいそうです。
しかし羽佐田さんは「必ず治す」ことを目指し、病院勤務を非常勤にして自身のクリニックを開院しました。
羽佐田さんは重度の吃音がある高橋さんに「必ず流暢に話せるようになる」と言い、高橋さんも羽佐田さんを信じて訓練を開始しました。
ともに吃音に苦しみ、一度は死さえ望んだふたりが出会い、その苦悩の根源を取り除こうとする戦いが始まります。
高橋さんは自らに厳しい練習を課し、ついに「流暢に話す」技術を身につけました。
居住地で行われた「吃音ワークショップ」でスピーチすることで、その訓練の効果をたくさんの人に見せたいと、高橋さんは大勢の人の前でスピーチすることを決意します。
その一方で、同じ「吃音ワークショップ」に登壇したのは、吃音者の姉という人物でした。
彼女は、吃音者だった弟を自死により失っていました。
明るい性格で誰にでも優しく、たくさんの友人がいたという飯山さんは、しかし誰にも悩みを打ち明けずにひとりで死を選びました。
看護師として働き始めた矢先のことで、いったいなにがあったのかと病院にも就労時の様子を尋ねますが、病院側はなにも答えようとしませんでした。
著者の近藤さんは職場でなにかあったのではと感じ、取材を申し込みますが、誠意ある回答は得られませんでした。
この件は家族が労災認定を求めて現在も係争中です。
吃音があるというだけで、平等に扱われない、過剰に圧力をかけられる、それがエスカレートしていじめのような形になることが職場では圧倒的に多いことが伺えます。
吃音は、ただ「どもる、うまく話せない」だけと思われがちですが、その症状に悩む人が一度は死を考えるというほど本人にとっては非常に重い症状です。
ただうまく話せないというだけでなく、就職で圧倒的に不利という現実もあり、書類選考は通過しても面接で落選したというケースが多いそうです。
現在、吃音は障害として認定されており、現在は「精神障害」としても「身体障害」としても手帳を交付しています。
また、「障害者差別解消法」が施行されてから吃音への配慮も広がってきたと近藤さんは語ります。
本人にとって症状が続く限り苦しみからは解放されませんが、それでも周囲の理解が進むことは吃音者にとってプラス要因であることは間違いないと思います。
吃音に限らずすべての障害、差異に関して「自分と違う」ということをもっと知り、理解することで互いの距離は埋められるはずで、その努力は双方がすべきだと私は思っています。
障害の有無ということではなく、そもそも「他人」は「自分」と違っていてあたりまえ。
互いの間に横たわる「違い」を埋めるには、互いが心を通わせる以外に方法はありません。
そしてそれは、ちょっとの気遣いや思いやりや笑顔ですぐに埋まるものなんです。
私が小学生のころ、同じクラスにうまく話せない男の子がいました。
おそらく吃音だったのだと思いますが、彼が一所懸命に話そうとするのを、子供だった私たちは「会話のテンポが合わないな」とは思っていましたが、それほど気に留めることもなく彼の口から言葉が出るのを自然に待っていたように記憶しています。
会話のテンポが合わないこと以上に、子供の私たちにとっては、「彼がなにを言うのか」という、「次の言葉」そのものへの興味しかなかったのだと思います。
そういう自然なことが、大人になるにつれて「中身」より「外側」ばかり気にするようになるのはなぜなんだろうと思います。
ガチャガチャをしたら、どんなものが出てくるかということだけが楽しみで、カプセルがどんなに立派でもボロボロでも、そんなことは気にしないはずです。
私たち大人はいつから、おもちゃよりもカプセルを気にするようになっていくのだろうと、なんだかもの悲しさをおぼえました。
本書を読んでいてたいへん興味深かったのは、吃音のメカニズムを解明しようと様々な研究が行われてきたという歴史です。
世界で初めて吃音の科学的検証が始まったのは1920年代、アイオワ大学で言語障害を研究していたリー・エドワード・トラヴィスによると記されています。
この頃は、ロンドンの学童へ行われた大規模な調査によって、吃音のある子供のうちの大多数が左利きを右利きへと矯正された子供であったことなどが統計として知られていました。
その結果をもとにトラヴィスは、大脳の左右半球どちらかが持つ優位性がバランスを崩したことにより吃音の症状が出るのではないかと仮説を立てます。
これは「吃音の大脳半球優位説」と呼ばれ、いわゆる「左利き矯正説」ともいわれたそうですが、その後の研究では反証も多く掲げられ、現在は否定されています。
しかし、吃音者の脳機能の研究では大脳の右半球が過剰に活動しているという結果があり、おもに言語をつかさどる左半球が機能の不具合を起こし、それを右半球が補おうとしているのではないかという検証などが行われているそうです。
さらにその後、アイオワ大学ではウェンデル・ジョンソンが「診断起因説」という仮説を打ち立てました。
これは「うまく話せない子供に母親や周囲の者が吃音だと注意することで当人に意識させ、それが吃音の起因となっている」という考えです。
ジョンソン自身が吃音者で、学校の先生に指摘を受けたことから症状が悪化したと彼が信じていたからだそうです。
そしてこの起因説を証明するために、ジョンソンの教え子たちはおそろしい実験を行います。
のちに「モンスター・スタディ」と呼ばれた悪名高い実験で、その内容は非人道的なものでした。
吃音症状のある子どもとない子ども計二二人を孤児院から集めていくつかのグループに分ける。そして、彼らの話し方について褒めたり叱責したりすることによってどんな変化が出るかを調べるというものだった。端的に言えば、つまり、吃音がない子たちに対して、症状がないにもかかわらず「あなたは吃音の兆候を示している、その話し方をやめなさい」などと数カ月にわたって注意し続けたら実際に吃音が生じると彼らは予測し、その変化を観察しようとしたのである。
この実験によって吃音のない被験者が吃音を発症したことはなかったが、結果、複数の被験者が実験途中から急に話さなくなったり、不安を訴えたりするようになった。何人かはこの実験を境に、その後精神的に深刻な問題を抱え出したともいう。
この実験については、ジョンソン自身もその後一切公表せず、長年知られないままだったが、二〇〇一年になってアメリカの地方紙によって発見、報道されたのをきっかけに広く知られ、大きな非難にさらされた。そしてその実験から七〇年近くが経った二〇〇七年になって、被験者に対してアイオワ大学が公式に謝罪し、慰謝料を払うという結果に至っている。
このように、吃音は精神的負荷から生じると信じる人が多く、また現在もその傾向は強いと感じます。
このような傾向は「自分にできる」ことを他人に強要することにもつながり、不登校状態の子供に精神論をぶつ大人や、育児に疲弊する母親に母性本能云々と説く人間と変わりなく、非科学的なことほど人は信じやすいように見て取れます。
しかし当然「根性論」などで解決できることではなく、その後も科学的解明は進み、吃音者の脳の構造などが少しずつ明らかになっているそうです。
最新の研究では、吃音のある子供とない子供の脳の神経画像を比較した結果、弓状束(神経線維の集まった経路のような部分)の神経線維の密度に有意な違いが認められたそうです。
また、弓状束や脳梁の増加速度に違いが認められるなど、大脳の左右半球をつなぐ部位に注目が集まっているようです。
脳には「可塑性」があり、環境によって神経回路の処理効率を高めたり、反対に低くしたりと大きく変化します。
可塑性により神経回路が発達することで症状の改善や治療ができるかもしれないという未来も見えてきているのかもしれません。
可塑性については、シナプスの解説がわかりやすいこちらのページがとても面白く、参考になります。
シナプス可塑性プロジェクト
公益財団法人 東京都医学総合研究所
脳の働きについては育児関連の本で目に触れることが多いですが、人間への脳の支配力のすごさを改めて感じます。
あれも脳のせい、これも脳のせい、本当になにもかも脳が人間社会を支配しているんだなぁと感服します。
「吃音ワークショップ」で高橋さんがスピーチした内容で、とても心に残る一文がありました。
訓練を始める前まで、人から何かうれしいことをしていただいても、『ありがとうございます』という感謝の言葉を言うことができず、いつも、より言いやすい『すいません』に言い換えていました。でもいまでは、『ありがとうございます』と、言えます。
言葉は、ただ伝えるだけのツールではなく、心を相手に差し出すための重要な表現なのだということを強く感じた一文でした。
2019.04.11追記
4月からニャ娘が小学校へ進学しましたが、学校からこんなお便りを配布されました。
「こんな心配はありませんか?」
という見出しで
・発音が気になる
・きこえが気になる
・言葉の発達が心配
・言葉を繰り返したり、伸ばしたり、つまったりする
この最後の「言葉を繰り返したり、伸ばしたり、つまったりする」にはこう書かれています。
「ぼ、ぼ、ぼくね」(繰り返す)
「ぼぉぉぉくね」(伸ばす)
「ん・・・・っぼくね!」(つまる)
話すときに身体に力が入る
これらの症状は吃音だなと、本を読んでいたのですぐにピンときました。
上記の症状が見られる場合には、小学校内に設けている専門の教室で指導を受けられるとのことです。
居住区のすべての小学校にあるわけではなく、発音を専門とする「ことばの教室」と、聴覚を専門とする「きこえの教室」というのが特定の小学校に設けられていて、偶然ですがニャ娘の通う小学校内にありました。
いまは学校で学童期の子供をここまでフォローしてくれるのかと、とてもありがたく、また心強く感じました。
子供のフォローを学校内で行うということは、症状のない子供たちへの周知と教育も同時に行われるということでしょうから、教育現場もずいぶんよくなっているんだなと隔世の感がありました。
なにしろ〇十年前の私の時代は、先生が率先して差別用語や体罰を生徒に振りかざしていましたから。。。(^_^;)
「みえるとか みえないとか」
ヨシタケシンスケ:作・絵
みえるとかみえないとか、違いがあるから人は興味深く面白い
「その島のひとたちは、ひとの話をきかない 精神科医、「自殺希少地域」を行く」
他人と自分の違いを知り、問題を解決することに慣れている人たち。
自殺希少地域で見た「生きやすさ」のヒント