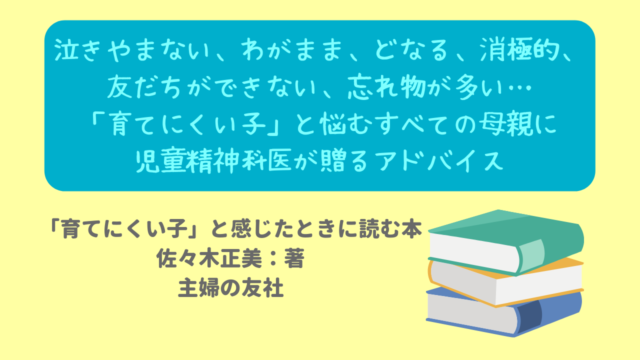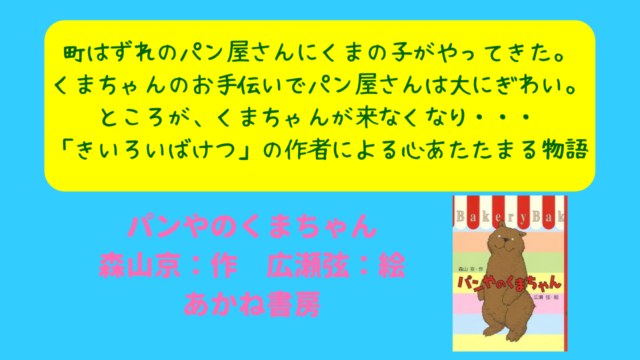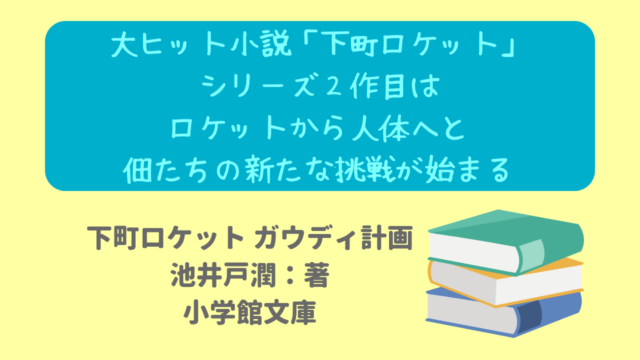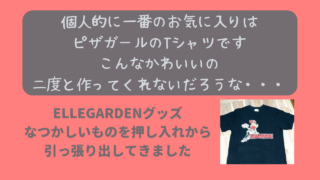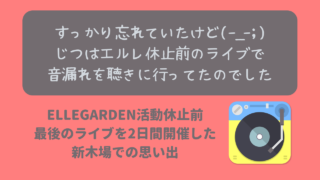八月十五日に吹く風
松岡圭祐:著
講談社文庫
あらすじ
「終戦」から72回目の夏、外務省で書類の束を読み込んでいる男がいた。
トルーマン大統領のポツダム日記、米国情報公報、シンクタンクからホワイトハウスへの意見書に、マッカーサーによる日本占領計画。
第二次世界大戦での日本降伏以前に米国内でやりとりされた書類の山から、最後に出てきた書類は「日本および日本領の最終的占領」と題する報告書だった。
その報告書の欄外に、小さく注釈が書かれている。
「一九四三年八月十五日に関するロナルド・リーンの報告に基づく分析により、注意警戒事項を削除」
注意警戒事項とは、「今後(註:終戦後)も非戦闘員による個人単位での玉砕、あるいは村や隣組など小自治体単位での反乱が起こりうる」というもので、日本人は民間人であってもアメリカ人への敵愾心が強く、極めて野蛮であると危険視されていた。
この、アメリカ全土の共通認識であった「日本人のイメージ」を、ロナルド・リーンなる者の報告が払拭させたらしい。
そして物語は、「終戦」の2年前、1943年の夏へと移ってゆく。
1942年、「ミッドウェー作戦の陽動作戦」としてアラスカ州アリューシャン列島の諸島に属するアッツ島とキスカ島を、日本軍が攻撃し占領した。
しかしアッツ島はアメリカ軍に奪還され、島にいた日本兵は殲滅させられる。
アッツ島をアメリカ軍に奪還され、キスカ島奪還も時間の問題と目されるなか、キスカ島に残る五千二百人の兵士を撤退させるべく立ち上がった男たちがいた。
すでに戦艦も数多く失われ、大国の攻撃が激しさを増すなかで、北限の孤島へ五千もの人間を残らず撤退させ、しかも救出に向かう隊も無傷で帰国する。
どんな奇跡が起ころうとも不可能と思われた救出劇だが、その不可能を可能にすべく知恵を絞り揺るぎない決意で臨んだのは、木村昌福(まさとみ)。
キスカ島撤退作戦の司令官に任命された彼は、アメリカ海軍に見つかることなくキスカ島へ上陸する方法を模索し始める。
一方、日本文学をこよなく愛し、アメリカ軍の日本語通訳に従事していたロナルド・リーンは、アリューシャン列島への通訳同行を命じられる。
アッツ島への総攻撃、日本兵を焼き尽くした惨状をその目で見たリーンは、この戦争がなんのために行われているのか、日本人が本当に「命を粗末にする民族」なのかと懐疑し始め、その思いは日々強くなっていった。
アリューシャン列島での戦闘を目撃し、そののち日本降伏の日を迎えたリーン。
日本天皇の玉音放送を翻訳するため、海軍大将であるレイモンド・スプルーアンスのもとを訪れた。
スプルーアンスが近日マッカーサー陸軍元帥と面会することを知っていたリーンは、どうしても伝えてほしいことがあると、粗末な紙の束を差し出した。
海図にびっしりと書き込まれた天気図を見せながら、リーンは語り出す。
日本人がどんな思いでキスカ島から撤退したのか。本当に日本人はハラキリや自殺願望の民族なのか--。
ニャム評
「千里眼」シリーズの著者・松岡圭祐による、キスカ島撤退作戦を描いた物語です。
本を開いて最初に記述されている
「この小説は史実に基づく
登場人物は全員実在する(一部仮名を含む)」
という一文が印象的です。
アッツ島、キスカ島は北海道から千島列島を伝って東へ連なる、アメリカ最北の列島の一部です。
Wikipediaの地図を見るとわかりやすいのですが、点在する島をたどるとアメリカがこんなに近くにあったのかと思わせられます。
Wikipediaより
アリューシャン列島
アメリカ本土を占領したと大本営は華々しく報道しましたが、実際には凍りついた土地に滑走路や建造物など作れるはずもなく、なにもできないまま兵士たちは取り残され、物資を届けることも救出することもできずにアッツ島上陸兵士は全滅しました。
キスカ島に駐留する五千二百もの兵士たちをも見殺しにすることは絶対に避けねばならないと、撤退作戦が決行されますが、アメリカ海軍がすき間なく見張るなかを無傷で全員救出するのは不可能と誰もが考えます。
この作戦の司令官に任命された木村昌福は、人命第一を掲げる当時は希少な軍人でした。
彼はどうやってキスカ島へ上陸するか考えたすえ、気象予報士とともに霧を詳しく調べ始めます。
濃霧にまぎれて島へ上陸し、速やかに兵士を撤退させようというのが木村司令官の作戦でした。
キスカ島に残された兵士たちに撤退作戦を伝えるにも、アメリカ軍に無線傍受されているため方法がありません。
そこで、暗号文で「玉砕」を思わせるような内容を発信し、反対に通常の発信では「ケ号作戦」と伝えます。
暗号文を解読したアメリカ兵はアッツ島と同じく玉砕命令が出たものと思い込みました。
「ケ号作戦」とはガダルカナル島での撤退作戦で使われたのと同じ作戦名で、それを傍受したキスカ島の日本軍通信兵は「きっと救出に来る」と信じ、一日で一番霧が濃い時間に全員が浜辺に集合するという日課を定めました。
本当に助けがくるのかどうかもわからない、いつアメリカ軍の砲撃が来るかも知れない、そんななかで一縷の望みを胸に、キスカ島駐留軍は骨と皮になっても生き続けます。
何度も霧の予報に失敗し、キスカ島へいつ向かうことができるか焦りを抱えながらも、救出隊は諦めることなく挑戦を続けます。
物語の終盤、ついに霧を味方につけ、キスカ島へ軍艦が接岸するシーンは涙を禁じ得ないほどの感動がこみ上げます。
著者の得意芸である伏線とその回収が見事で、物語が進むほど驚きや感動の発見が随所に埋め込まれており、読み進むのを止められない面白さもあります。
とくに終盤では圧巻の巻き返しが怒涛のごとく描かれ、ページを繰る指がどんどん速くなっていきます(私はキンドルで読みましたが笑)。
大戦ものは悲壮なものが多く、積極的に手が伸びないのが正直なところです。
知らなければいけないけれど、やはりどうしても気持ちが沈みます。
そういうなかで、「絶対に誰ひとり死なせない」と強い決意で生き抜いた人たちと、それを見守った人たちの話は救われる思いがしました。
物語のラストで、登場人物の従軍記者・菊池の思いを綴る一文があります。
なによりいまの木村には笑顔がある。家族と喜びを分かちあっている。
人として生きるとき、それ以上なにを望むだろう。最大に等しい幸福を手にしているというのに。
最大に等しい幸福。
それはきっと、世界中のどんな人も同じであるはずです。
もうすぐ「終戦」の日がやってきます。
本来、8月15日は玉音放送があったのみで、ポツダム宣言受諾が8月14日、降伏文書調印が9月2日のため、8月15日が「戦争の終わった」公式の日ではありません。
玉音放送でも「降伏」とか「敗戦」という言葉はなかったため、あの日を日本国の敗戦と位置付ける絶対的な根拠にはならないようです。
本文中で菊池がこんな回想をしています。
戦争が終わった日は、人によってちがう。
ただし、みなが揃って平和を誓う日を設けるなら、それでいいのかもしれなかった。
全員が行動を同じくする。
それが戦争でないのなら。
作中の主要人物であるロナルド・リーンは日本文学研究者のドナルド・キーンさんですね。
彼がマッカーサーへ言伝をしなかったら、日本は他の植民地と同じく米国領地になっていただろうと本作では示唆します。
いま私たちが平和で安全な「日本」という国に暮らしていられるのは、たくさんの人の想いによって築かれた幸せなのだろうとしみじみ思わされました。
なお、本書での「八月十五日」とは、アメリカ海軍がキスカ島奪還のため上陸した日とされています。
1943年、すでにもぬけの殻になったキスカ島へ激しい攻撃を加えた日。
そして1945年、ロナルド・リーンが日本人の心を代弁した日。
殺し合いがいかに無益で愚かなことであると、人々はいつ気づくのでしょう。
日本国中で「平和」について祈る日が、もうすぐやってきます。