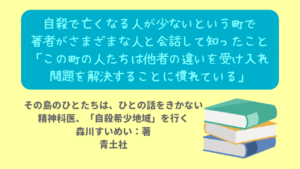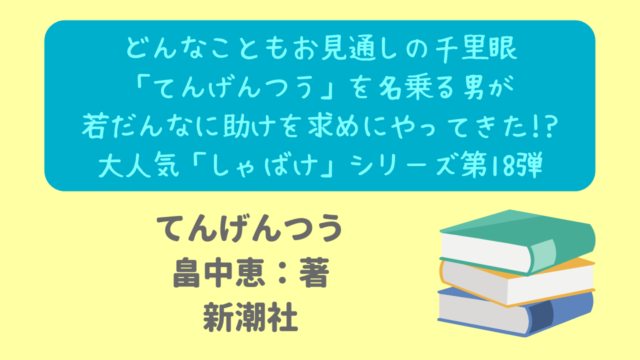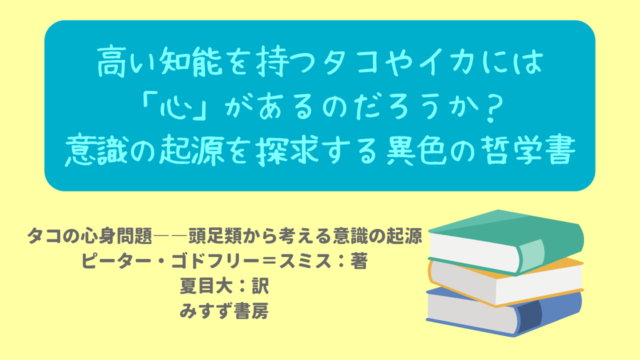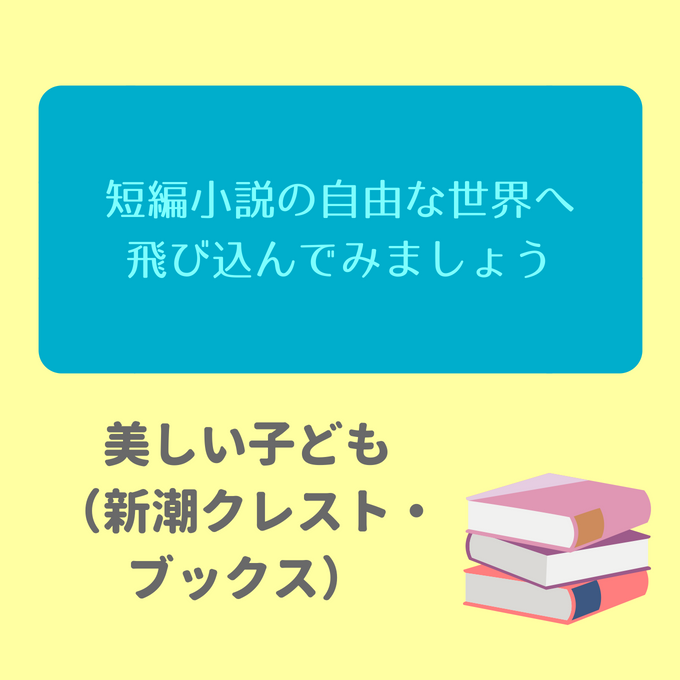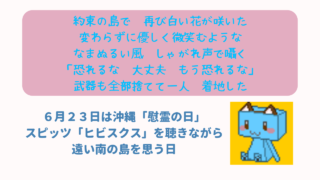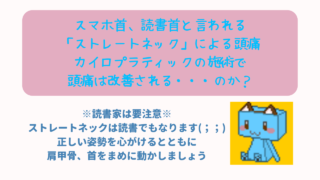孤独と不安のレッスン よりよい人生を送るために
鴻上尚史:著
大和書房
あらすじ
孤独には、「本物の孤独」と「ニセモノの孤独」がある。
ひとりであることが、みじめで、恥ずかしく、かっこわるいことだと思い込んでいるのが「ニセモノの孤独」である。
では、「本物の孤独」とはいったいなんだろう。
自分と向き合い、対話することが「本当の孤独」であると著者は語る。
誰かの言葉に振り回されず、たったひとりで考え、答えを見つけること。
「本当の孤独」は、とても豊かな時間なのだ。
不安にも、「前向きの不安」と「後ろ向きの不安」がある。
「後ろ向きの不安」とは自分を振り回す不安であり、「前向きの不安」はエネルギーを与えてくれる不安である。
孤独と不安は、人間が生きているかぎりついてくる。
しかし、それらは「悪いもの」なのだろうか?
人間として成長し、豊かな生活を送るために、孤独と不安の練習をしよう。
鴻上尚史流の「よりよい人生を送るためのワークショップ」が開講。
ニャム評
鴻上尚史さんといえば、「第三舞台」の主宰であり、劇作家、小説家、エッセイスト、そして「オールナイトニッポン」DJなど幅広い活動で知られています。
私は鴻上さんが大好きで、コーカミさんと親しみを込めて呼んでいます。
さて、「孤独と不安のレッスン」は2006年に発行された本ですが、いまの時代にこそ読まれるべき内容だと感じます。
競争社会が激化し、新型コロナウイルスにより社会は分断し、フェイクニュースによって陰謀論を本気で信じ込んでしまう人が後を絶たないような世界で、人は孤独を感じ、不安を感じています。
いつの時代も孤立や不安にさいなまれるような出来事はそこかしこにあるものの、その影は年々色濃くなっているように思います。
孤独や不安に耐えられず、生きるのがつらいと感じることが多い世の中で、孤独と不安の耐性をつけるべく書かれたのがこの本です。
孤独とはなにか、不安とはなにかを論理的に理解し、むやみに振り回されないためのレッスンです。
まず、日本人が(と、ざっくりくくるのは乱暴かもしれませんが)もっとも恐れ、忌み嫌うものが「孤独」ではないでしょうか。
「ぼっち」になることを極度に恐れ、なんでもいいからとにかくどこかのグループに属したい。
なぜかといえば、「ひとりぼっちはみじめだ」という思想があるからです。
日本において「ひとりぼっちはみじめ」という思想はもはや信仰ではないかと思うほど強力な呪縛です。
「ひとりはさみしい」と思い込むのはなぜか、その理由をコーカミさんは「あの歌」だと推察します。
「一年生になったら」、そう、あの歌です。
私もあの歌がだいきらいです。
だって100人も友だちできるわけないじゃん。
そんなの友だちじゃなくてただの知り合いじゃん。
コーカミさんもひとつのネタを面白く引っ張る天才だなと思いますが、この歌についてガッチリ論破しています。
僕は、子供の頃に歌った、あの歌がけっこう大きな原因になっていると思っています。
「1年生になった〜ら〜、友達100人できるかな」です。
声を大にして言いますが、友達は100人できません。それはムチャです(笑)。大人でも、100人友達がいる人なんていません。100人のうち、多くは友達ではなくて知人です。本当に100人の友達を作ろうとしたら、人間関係に忙殺されます。
まして、充分な交通費も飲食代も用意できない小学1年生に100人の友達を作ることは、断言しますが、不可能です。
59ページ 「それでも「一人はみじめ」と思ってしまう理由」より引用
ただのわらべうたですが、小さな子供にインパクトを与えるには十分です。
そして、コーカミさんはこう続けます。
この歌の一番の問題は、「友達が多いことは無条件でよいこと。友達が一人もいないことは、無条件で悪いこと」という価値観をわずか5、6歳の子供に刷り込んでいることです。
友達の大切さと難しさを歌うのならともかく、ただ、「友達100人」を歌い上げるのは、あまりにも能天気で罪深いことです。
そして、大人達は、1年生に向かって、何の疑問もなく、「友達できた?」と聞きます。その質問の繰り返しが、子供達に、「友達ができないことは、間違ったこと」という価値観を刷り込むのです。
結果、学校でも家庭でも、「友達の多いことはいいこと」「友達のいない人は淋しくてみじめで問題のある人」という価値観が、なんの問題もなく流通していくのです。
イジメのひとつの原因が、この「友達100人絶対至上主義」だと言うのは間違いでしょうか?
60ページ 「それでも「一人はみじめ」と思ってしまう理由」より引用
「一年生になったら」をここまで論理的に語った文献も少ないでしょう。
でも、コーカミさんの言いたいことはよくわかります。
自分が親になってみて強烈に感じるのですが、親(とくに母親)が「友だち100人」を良きこととし、自分の子供にそれを課そうとしているケースを散見します。
「みんなと仲良くしようね」とお母さんたちは子供に呪いをかけます。
みんなって誰?と私は思うんですが、「みんなと仲良し」という抽象的な呪文は日本社会では正義です。
まど・みちおさんが悪いわけではないのですが、時代が完全にずれているのだろうと思います。
「一年生になったら」の歌詞世界はもはやユートピアなのでしょう。
蛇足ですが、我が家のニャ娘も「みんな」に振り回されたことがありました。
保育園で一緒だった子と同じ小学校へ進学し、放課後の学童クラブで一緒に遊んでいたころ、「おにごっこするといつもニャ娘ちゃんがおになの。タッチすると『バリアしてたからダメー』って言って代わってくれないの」と悲しそうに話していたことがありました。
私は「いやだったら、その子たちと遊ぶのをやめて違うことをしたら?」と言いました。
ニャ娘はさみしかったようで「でもみんなと遊びたい」と言い、その後もがまんしておにを続けていたようでしたが、数日後にすっきりした表情で言いました。
「いつまでもニャ娘ちゃんがおにで、もうつまんないから、○○ちゃんたちと遊ぶのやめたんだ」
そして、ひとりで本を読んで過ごすことに決めたそうです。
たった6歳で「孤独」を自分で選んだニャ娘の強さに驚きましたが、これは私自身も「孤独」が好きだということが大きな影響を与えているのだろうと感じます。
さて、「ひとりはみじめ」と思い悩む人は、この本で「孤独」のレッスンを受けることができます。
「孤独」とはなにか、ひとりでいることの本当の価値、人間として成長することについて解説してくれます。
コーカミさんは「世間」研究家だと私は勝手に思っているのですが、とにかく「世間」というものについて熟知しています。
そして、人がひとりぼっちを悪として苦しむ理由を「世間」が原因だと論じています。
「世間」とは、「みんな」とも言い換えられます。
あなたが悪口を言われたとき、「みんなもそう言ってるよ」と付け加えるだけで、ショックは何倍にも増大します。
みんなって具体的に誰だよ、と思うのですが、「みんな」と言われてしまうと、世界中から全否定されたような衝撃を受けてしまいます。
「みんな」って便利な言葉ですよね。
でも、論理的に考えれば、「みんな」イコール「そこに属する全員」とすると、全員の意見が一致することなんてそうそうないはずです。
しかし、「みんな」という呪縛にからめとられて身動きが取れなくなってしまうのです。
でも、大丈夫です。
「世間」という呪縛から解放される方法を、コーカミさんはよく知っています。
コーカミさんに「世間」を語らせたら右に出る者はいないというくらい、コーカミさんは熟知しています。
「ぼっち」に過剰に苦しんでいる人は、この本をじっくりと、できれば知っている人がいない静かな場所で読んでください。
「孤独」をよく理解したら、次は「不安」についてのレッスンです。
不安というものがなんであるか、不安をどう取り扱えばいいかについて具体的に解説しています。
不安は誰にでもあります。
あって当たり前のものです。
しかもやっかいなことに、不安は自分の中で作られるものです。
不安と向き合う方法を知らないと、不安が不安を生み、無尽蔵に不安が増産されてしまいます。
この本では様々な方法が具体的に解説されていますが、なかでも私がいいなと思ったのは「おみやげ」の話です。
不安そのものにフォーカスを当て、不安を考えれば考えるほど、不安は成長するとコーカミさんは言います。
だから、不安そのものを見すぎないように、なにか別のことに意識を移せばいいのです。
つらくてたまらなくなったり、不安でいてもたってもいられなくなったりしたら、誰かに何かをあげることを考えましょう。
なんでもいいのです。
物でもいいし、お話でもいいし、僕はそれを「おみやげ」と呼んでいます。
笑顔でも、おみやげになります。
誰に何をあげようと考えるだけで、あなたは不安にフォーカスすることを自然にやめることができます。
そして、この方法の素敵なことは、「おみやげ」をあげる関係ですから、やがて、「おみやげ」の「お返し」がくる可能性があることです。
もちろん、お返しを期待しているわけではありません。
ただ、不安に苦しむ人は、みんな、「自分の世界」だけで苦しみがちです。
「自分の世界」にフォーカスを当てて、ずっと苦しむと、その世界は広がりません。
結果、自分の不安だけを見つめ続けることになるのです。そして、不安は成長するのです。
162、163ページ 「つらくなったら、誰かに何かをあげる」より引用
コーカミさんのすてきなところは、「誰かにちょっといい働きかけをする」ことが根底にあることです。
他者に対する向き合い方がすてきだなといつも感心します。
人はどうしたって、ひとりで生きていくことはできません。
社会に属して生活する以上、一人暮らしだろうとなんだろうと、「ひとりぼっち」として生きていくのは不可能です。
だからこそ、自分と関わりのある人には「いい働きかけ」をしようと心がけることは、大切なことだと思います。
孤独に苦しむ人たちを、正直なところ、私はあまり理解できないというか、共感できていないと思っています。
もう少し正確に言うと、「ニセモノの孤独」にさいなまれる人たち、でしょうか。
私は小さいころから人見知りで、家族からも「変わり者」と言われているような子でした。
空気を読むのが下手で、「みんな」に合わせることが苦痛で、かなり早くから「ひとりぼっち」だったように思います。
小学生のころはたぶん面白いこと、楽しいことがあまりにもなくて、そのころの記憶がほとんどありません。
中学生になるとますます「みんな」が苦手になり、高校ではとうとうクラスで話す相手がひとりもいませんでした。
およそ12年ほど、学校でなにをしていたかといえば、本を読んでいました。
教室にいてもやることがなく、休み時間は言ってみれば地獄です。
だからといって、たかだか15分くらいの休み時間のたびにどこかへ行くわけにもいきません。
時間をやり過ごすために本を読むしかありませんでした。
読む本がなくなって、図書館の本棚の「あ」から借りて読んでいたころもあります。
当時を思い出すとちょっぴり狂気すら感じますが。笑
本を開いてその物語の中に飛び込むことで、自分の皮膚一枚をへだてた外側の世界を強制的にシャットダウンし、文字の中にいる登場人物を友だちとして、ひたすら時間が過ぎるのを待っていました。
いくら変人でも、やはり日本の「世間」で変人を貫くのはなかなかに苦しかったのだと思います。
私はそんなふうにして、「孤独」のレッスンをひとりで行っていました。
いまはこんなに親切なテキストがあっていいなと思います。
でも、私は自分がひとりぼっちでみじめだとは露ほども思っていませんでした。
まったくもって、「友だちがいなくてひとりぼっちの自分がみじめで恥ずかしい」などとは1ミリも思ったことがありません。
なんでしょう、この自己肯定感の高さは。
小学生、中学生のころは、家族がいたことで支えられていたのだろうと思います。
かなりめちゃくちゃな家庭環境でしたが、それでも母ときょうだいの存在はとてもありがたいものでした(そこに父が出てこないということで察しがつくかと思いますが)。
高校生のころは、部活が私の人生を大きく変えました。
ブラスバンド部に入り、そこで出会った友人が、私の存在を深く理解し受け入れてくれました。
互いに大切に思い、支え合う友人ができたことで、「大切な人がいれば、それ以外は不要だ」とはっきり理解することができたのです。
本書でもコーカミさんが言っています。
どこかで、必ず、あなたは、あなたが知り合えてよかったと思える人と出会います。
あなたが、「本当の孤独」の中で、成長すればするほど、その確率は高くなります。成長すればするほど、出会う相手は素敵になります。
無理して笑う必要も、退屈な話に相槌を打ち続ける必要も、人の悪口に同調する必要も、発言が悪意に取られないかと心配する必要も、ない相手です。
あなたのクラス35人が全員、あなたを無視しても、隣のクラスか別の学年に一人は、あなたの「本当の孤独」を理解する人がいるはずです。その人は、先に、「本当の孤独」を味わっている人です。
あなたの職場が、3人しかいなくて、3人全員があなたを毛嫌いしていたとしても、取引先か別の階の会社の人か宅配便の人か、一人はあなたの闘いを理解してくれる人がいるはずです。
あなたの近所の主婦が全員、あなたを嫌っていると思っても、どこかできっと、意外に近所の素敵な主婦と出会うのです。
僕の個人的経験だと、あなたの周りに30人いれば、一人はあなたの「本当の孤独」との闘いを支援してくれる人が現れます。
29人の人に無視され、嫌われたとしても、あきらめることはないのです。
46、47ページ 「「本当の孤独」を生きると新しいネットワークが見つかる」より引用
これ、本当です。
コーカミさんありがとう。
こうして、孤独と向き合ってきた人に「間違ってないよ、それで正解だよ」って言ってくれてありがとう。
心からそう思います。
両手の指で数えても余るくらいしかいなかったとしても、大切な誰かがいれば、それ以外の場所で「ひとりぼっち」になっても大丈夫。
そして、本はきっとあなたの「本当の孤独」に寄り添ってくれるはずです。
学校という場所は、私にとって牢獄のようなものでした。
物理的に逃げることのできない場所で、本は私にとっての「逃げ場」でした。
これは、ニャ娘の小学校の先生と話したなかでも同意見でした。
本が大好きだったという先生はみんな「逃げ場だった、ということもありますけどね」とお話しされていました。
たとえ逃げ場だったとしても、読書は必ずなにかが自分の中に残ります。
そして、そのなにかが、思いがけないところで自分の支えになったり助けになったりするものです。
この本の一番最後に、コーカミさんからのメッセージが記されています。
とてもとてもやさしいメッセージです。
その言葉が、どうかたくさんの人に届きますようにと、心から願います。