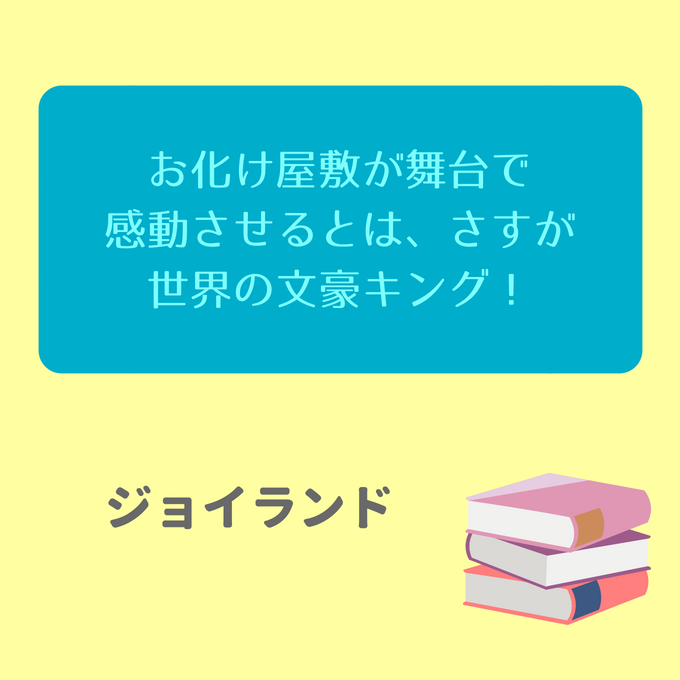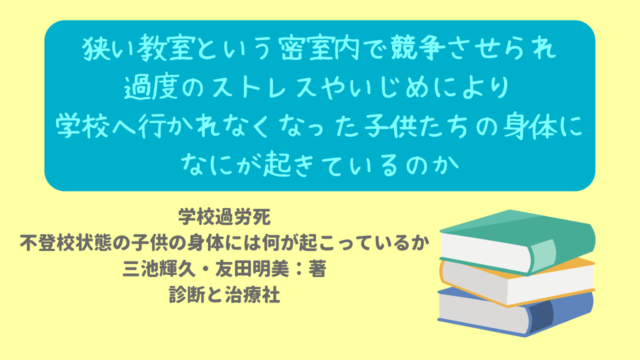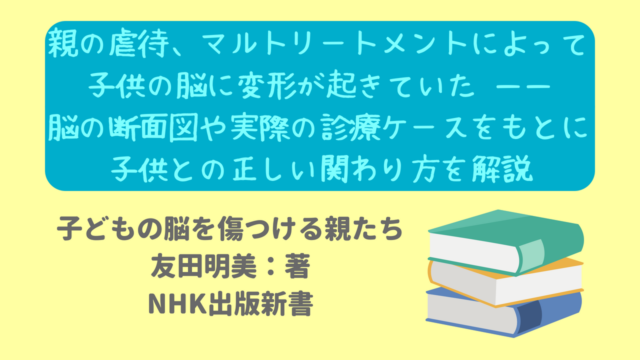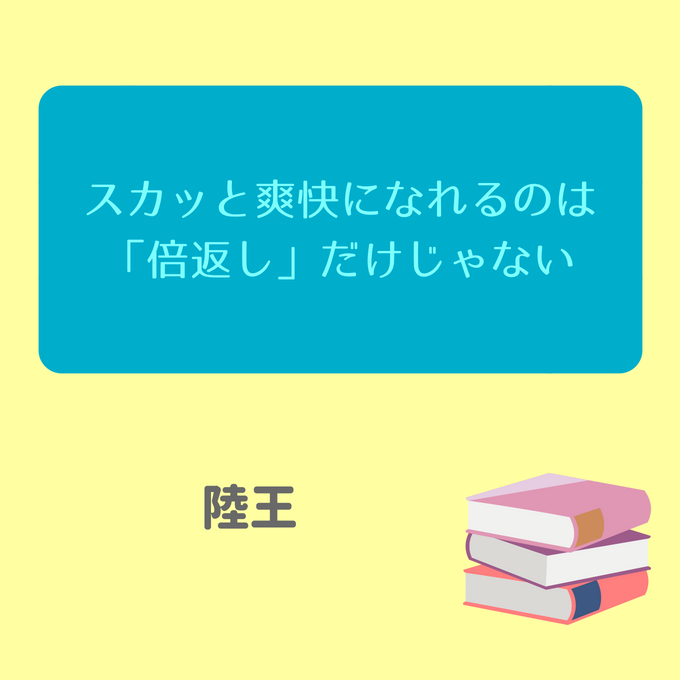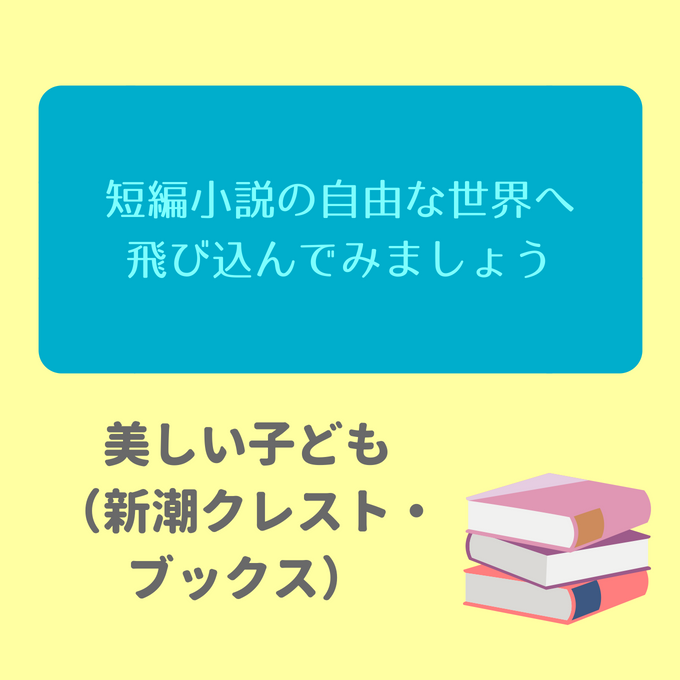心臓を貫かれて
マイケル・ギルモア:著
村上春樹:訳
著者のマイケルは「ローリングストーン」誌のライターとしても有名な人だそうです。
この本は、マイケルの実の兄、ゲイリー・ギルモアについて書かれたノンフィクションです。
殺人罪で銃殺刑を望み、その是非でアメリカ内外が大きな衝撃を受けました。
本書ではゲイリーがなぜ残忍かつ冷酷な殺人を犯したのか、ゲイリーの誕生より前のギルモア一家の歴史を紐解いていきます。
正直言って、ギルモア一族の話はかなり重苦しくやりきれない歴史がほとんどで、そうとう気が滅入る話でした。
が、その泥沼のような重く息苦しい呪いが家族全員を飲み込み、蝕んでいく様子が下巻から描かれていき、最後はその呪縛から逃れられなかった彼らを心から気の毒に思い、そしてまったく他人事と思えない気持ちになりました。
世間で「殺人犯」と聞けば、たいていの人は憎しみや怒りを感じることだと思います。
それが自分の「世間」から遠く離れていればいるほど。
しかし、それがもし自分と近しい人物であった場合、状況は一変します。
いかに実直で勤勉に暮らしていたとしても、そんな自分とはまったく関係なく、その近しい人物の所業によって、ある日突然自分の人生を大きく歪められる。しかも、単純に憎むことすらできず、愛があるゆえにいっそう苦しまされることになる。そういう状況に成り得る可能性を誰もがはらんでいるのだと、この本で痛切に知らされます。
どんな「悪」であっても、悪になった過程が必ずあって、その過程が不可避であった場合、人間は「悪」になることを回避することは不可能なのかと、目の前が暗くなるような気持ちになります。
その圧倒的な悪の前では、ささやかで普遍的な善などまるで役に立たないような絶望感をおぼえます。
「神戸児童殺傷事件」の加害者が手記を出版したことで世論が揺れましたが、あの本の出版に関しては私個人も非常に不愉快に思いました(被害者遺族への配慮の欠如と、二重、三重の被害に遭わせたことに対する嫌悪感です)。
しかしその反対側には、マイケルと同じ立場の人も存在します。
https://this.kiji.is/239447917088112646
加害男性の家族が殺人を犯したわけではないにもかかわらず、その罪は「世間」によって家族や親族にも着せられ、死ぬまで許されることはないというのは、希望を見出すのが非常に困難な状況だろうと思います。
そして、こうしたことを見るほどに、自分以外のものに対して軽々しく論じることなどなにひとつできないのだなと思いました。
村上さんの解説にあった一文を引用します:
ゲイリー・ギルモアの呪縛と悲劇はもう一度、我々の前にありありとよみがえってくる。またもっと大きな視野で括るなら、アメリカという国家の呪縛と悲劇の再現でもある。両者に共通したテーマは、愛と暴力だ。激しい愛と、激しい暴力。ゲイリーは常に愛を求めるが、多くの場合、それは暴力で報いられる。その結果彼は、愛を求める作業と暴力の発露を、同一の根を持つ行為として捉えるようになる。深い情愛と、目を見張るような残忍さは、ゲイリーという人間の精神の中でごく自然に並立するようになる。ひとつのコインの裏と表である。
アメリカも同じだ。歴史的に見てアメリカそのものが、激しい暴力によって勝ち取られ、簒奪された国家であることを思えば、その呪いが今ある人々を激しく規定することも、また理の当然であると言っていいかもしれない。アメリカの建国にあたって人々が光として高くかかげた、理性と整合性への愛は、結果的に暴力によって報いられることになった。そしてもたらされるのは、圧倒的なまでの荒廃だ。
(中略)
マイケルが勇気を振り絞ってこの本を書き上げたことによって、果たしてゴーストの追跡からうまく逃げおおせるのかどうか、僕にはもちろんわからない。僕にわかるのは、この物語を読んだ多くの読者が、本の最後のページを閉じたあとで、おそらくはそれぞれのゴーストに向かい合うだろうということだけだ。多かれ少なかれ、向かい合わざるを得ないだろう。もちろん僕も、その「向かい合わざるを得ない」読者の一人であった。
(引用ここまで)
一言で言えば絶望の物語ですが、愛とはなにか、血のつながりとはなにかということをとても深く考えさせられる本でした。
人生には目をそらすことのできない場面が訪れる可能性もあります。
そのときに、そこから逃げるのか、地を這うようにしてでも生き延びるのか、この本は究極の選択を迫ってきます。
おすすめかどうかはわかりません(笑)。
ただ、自分がもしかしたら「そうなったかもしれない」人生の分岐のひとつを覗き見ることはできるかもしれません。