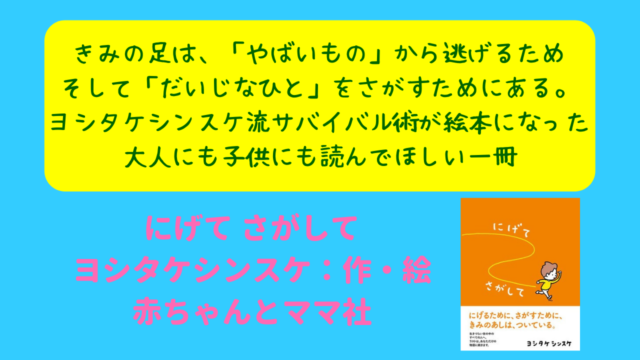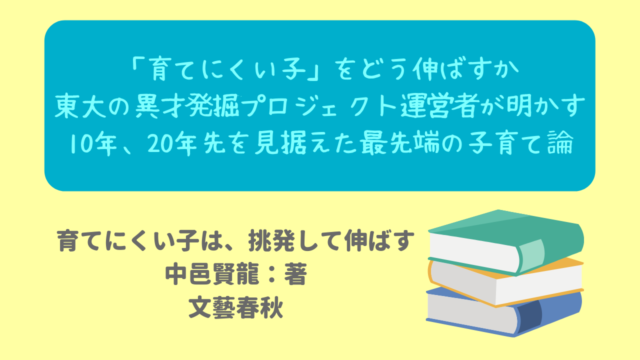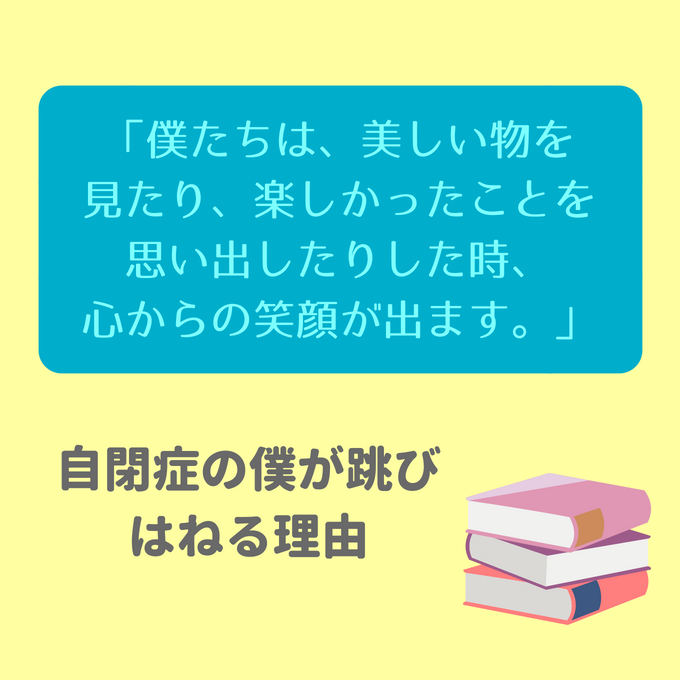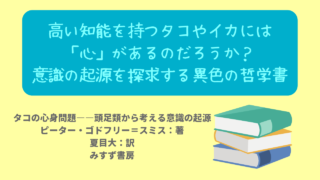たたかう植物―仁義なき生存戦略
稲垣栄洋:著
筑摩書房
あらすじ
じっと動かず、静かに存在する植物たちはしかし、私たちの目に映らない世界で苛烈な戦いを日々繰り広げている。
光合成のため光を奪い合う植物同士の争いや、植物を食べる動物を撃退するため毒やトゲを生み出した徹底抗戦、さらには自らを食べさせることで種を拡散させる戦略まで、ありとあらゆる方法で生き延びる道を模索してきた植物の歴史と知恵を紹介する。
本書を読んだあとは、草木を愛でる穏やかな気持ちから、たくましい戦士に舌を巻くような思いへと読者の心を一変させるような衝撃のエピソードが満載。
ニャム評
私は草木が大好きです。
花よりも、葉や木の幹などが好きで、木がたくさん立っている場所にいるととても穏やかな気持ちになります。
が、しかし!
これこそがすでに木の「毒」にやられているのだと知り、この本を読んで度肝を抜かれました。
この説明は後に譲るとして、本書の概要をご説明しましょう。
タイトルのとおり、本書は植物の生存戦略について紹介しています。
植物は光と二酸化炭素で光合成し、成長する生物ですね。
ですから日当たりのいい場所は植物たちの争奪戦となります。
まさに日照権を求めて、植物同士は何万年も戦ってきたわけです。
少しでも日光が当たるように、ある植物は葉を広げるより先につるをどんどん伸ばし、ある植物は葉の裏に吸盤を持って周囲のものに張りつき、さらにある植物はトゲをほかの植物に絡ませ、誰よりも上を目指しました。
このように姿を変えて、ほかの植物を出し抜くため進化を遂げてきたのです。
また、敵は植物に限りません。
植物を食料とする動物も大敵です。
はるか昔は恐竜、そして現代ではゾウやウシなどをはじめとする数多の草食動物に食べられてきました。
なにもせず、ただ食べられ続けていたら、あっというまに絶滅してしまいます。
そこで植物は自分の体内で毒を生み出しました。
栄養の一部を貯めて毒を作り出すのです。
自分自身の繁殖には毒は不要であり、コスト高でもありますが、その場から逃げられない植物の最大の防御策だったのですね。
実際、恐竜絶滅要因の仮説として、「アルカロイド中毒説」なるものがあるそうです。
被子植物が進化をする中で、食害から逃れるために、アルカロイドという毒成分を身につけた。そして、この植物を食べた恐竜たちが中毒死していったというのである。
現代でも「生きた化石」と呼ばれるような原始的な被子植物には有毒植物が多い。
被子植物が毒性物質を獲得した明確な理由については、よくわかっていない。しかし、少なくとも被子植物の毒は恐竜に甚大な被害をもたらしただろうと考えられている。
恐竜を毒殺したというから驚きです。
身近で見られる植物としては「セイタカアワダチソウ」が例に挙げられています。
根から様々な化学物質を出すことでほかの植物にダメージを与えたり、種子の発芽を阻害することで自身が有利に繁殖するわけですが、ほかの植物の成長を抑制する働きを「アレロパシー」と呼ぶそうです。
このアレロパシー効果を強く発揮する植物がセイタカアワダチソウで、根から出す毒によりほかの植物の成長を邪魔して自分だけ成長するわけですが、もちろんほかの植物だって黙ってはいません。
セイタカアワダチソウの毒に対抗すべく、様々な策で攻防を繰り広げてきました。
しかし、セイタカアワダチソウは北アメリカが産地で、日本には生えていなかった植物です。
つまり外来種ですね。
これが戦後日本に持ち込まれ、在来種であった日本の植物はセイタカアワダチソウの毒に対抗する術を持たず、あっというまにやられてしまいました。
国立環境研究所の「侵入生物データベース」では、セイタカアワダチソウは「日本の侵略的外来種ワースト100.外来生物法で要注意外来生物に指定された.」というなかなかにショッキングな紹介がされていました。
侵入生物データベース > 日本の外来生物 > 維管束植物 > セイタカアワダチソウ
国立環境研究所
このように正面から徹底抗戦を繰り広げる植物ばかりかといえば、そうではありません。
できれば戦いを避け、争いの少ない土地で暮らすことを選択した植物もいます。
それが砂漠に生息するサボテン類や、悪条件の土地でも生えてくる雑草です。
サボテンや雑草は強い植物と思われがちですが、実際には好条件の土地で多種と争うことを避けた「弱い植物」なのだと著者は語ります。
サボテンは葉の代わりにトゲを作って葉の面積を極限まで小さくし、水分の蒸発を防ぎ、さらにトゲを密集させることで光を錯乱させて茎に光を当てないようにし、温度が上がらないようにしています。
雑草は地面の下に種子をたくわえておき、自分が抜かれてしまうと、日当たりのよくなった土からまたすぐに発芽するようになっています。
これは「シードバンク(種の銀行)」と呼ばれ、自分が抜かれてしまうことを前提に種をたくわえておくのです。
このようにして、悪環境でも生きられる術を身につけることで、ほかの植物と住み分けをしているのです。
このように、さまざまな戦略で生き残ってきた植物ですが、なかでも高度な戦略である「毒」が、なんと人間にだけは効かなかったというのです。
苦味や辛味を持つ野菜類は、動物からの食害を防ぐための防衛術でした。
ところが人間は、タマネギやとうがらし、さらに熟す前の緑色のピーマンなどを「うまいうまい」と言って食べてしまいます。
また、植物の持つ毒には神経毒というものがありますが、人間の体内に毒が入るとそれを無毒化して排出しようと活性化します。
さらに、毒によって異常をきたしたと感じた脳は、鎮痛作用のあるエンドルフィンを分泌するのです。
「脳内モルヒネ」とも呼ばれるエンドルフィンは、疲労や痛みを和らげる働きをします。
そのため、チョコレートやコーヒー、タバコなどに含まれる「神経毒」を摂取すると、気持ちよくなったりリフレッシュしたような快感を得られるのだというのです。
森林浴でリフレッシュ!なんて言っていますが、木が出している毒成分に体が反応した結果、爽快感を得ていたのだとは衝撃です。
そのほか、果実を食べさせることで種を遠くへ運んでもらおうという戦略も、じつはその「運び屋」を鳥類に設定していたのではという興味深い解説があります。
赤色は波長が長く、ほかの色に比べて遠くまで見えるという特性があるそうです。
加えて哺乳類は赤が見えにくく、鳥類は赤を視認できるため、種子が熟した段階で果実を赤く変色させて鳥類の目に留まりやすくしたのだと説明されています。
「運び屋」を鳥類にした理由は、哺乳類だと歯で種子ごとかみ砕かれてしまうおそれがあることと、腸が長く排泄までに種子の状態が正常に保たれない懸念があること、それに比べて鳥類は種子を丸飲みにする可能性が高く、すぐに排泄するため種子が傷つくこともないということです。
というか、そんなことまで植物が知っていてそのように進化したのかどうかはわかりませんが、果実が赤い理由ひとつを取っても、驚くような話ばかりです。
そんな植物たちの知略も、なぜか人間にだけはことごとく効きません。
哺乳類は赤色が見えにくいと先述しましたが、人間だけは赤色を見ることができるようになったのです。
信号の警告にわざわざ赤を使うほどですから、人間にとっても赤色は視認しやすい色ということになります。
いつどのように赤色を視認できるようになったかはわかりませんが、とにかく哺乳類で人間だけが赤い果実を見つけて食べるようになったというわけです。
人間とは本当に不思議な生物ですね。
本書の魅力は植物の知られざる能力について堪能できる点ですが、著者の語り口の軽妙さとあふれるほどの植物愛も高ポイントです。
「日本人が雑草をひいきする理由」
「植物が他者との共存関係を築くため相手に与える様は『与えよ、さらば与えられん』と説いたイエスよりも早く神の境地に達していた」
などという独自の見解は、植物の擬人化が激しすぎて思わずクスッと笑ってしまいます。
植物の戦いの歴史を紐解きながら、最後に著者は人間と地球との関わりについて述べています。
もともと地球は二酸化炭素で覆われていたが、その二酸化炭素を植物が吸収し、物質を錆びつかせる有害な酸素を大量に吐き出すことで地球の環境を大きく変えてしまった。
30億年ものあいだ酸素を作り出し、それがオゾン層となって地球を覆い、結果的に紫外線を弱めたことでさまざまな生物が上陸し生態系を発展させていった。
つまり「豊かな生態系」を作り出したのは植物であり、現在の地球ひいては人間の誕生も植物の生み出した酸素という恩恵によるのである、と。
そして非常に高度な文明を持った人間は、地球を「もとの姿」に戻そうとしていると著者は言います。
人類は、植物が勝手に作り上げた地球の環境を本来あった元の姿に戻そうと懸命だ。
化石燃料を燃やしては二酸化炭素を排出し、地球の気温を温暖化しようと懸命に励んでいる。
二酸化炭素濃度が高く、温暖な環境はまさに植物が誕生する前の原始の地球の環境そのものである。
さらにはフロンガスを排出し、植物が勝手に作り上げたオゾン層の破壊にも取り組んでいる。人類の取り組みによってオゾン層には、大きな穴が空き始めたという。植物が生まれる前の地球のように、地球上に有害な紫外線が降り注ぐのは時間の問題だろう。
このように痛烈な皮肉で本書を締めくくっています。
我々人間だけが突出した知恵を持ち、その結果、地球を「生物の住めない星」にするとは、なんとも皮肉なものです。
これから私たちはどのように生きるべきか、植物に教えを乞うべきなのかもしれません。
「タコの心身問題――頭足類から考える意識の起源」
心(mind)とはいったい、どのようにして生じたのか。
高い知能を持つタコやイカの驚くべき行動から「意識の起源」を探求する哲学書