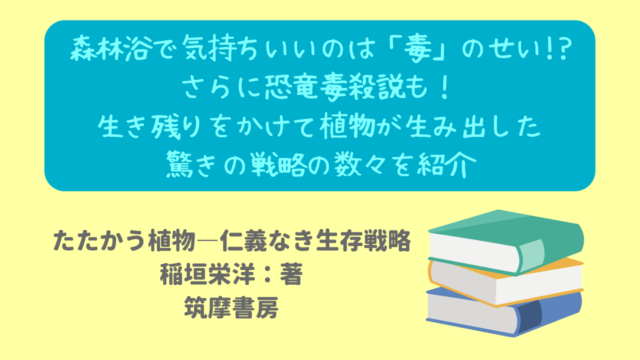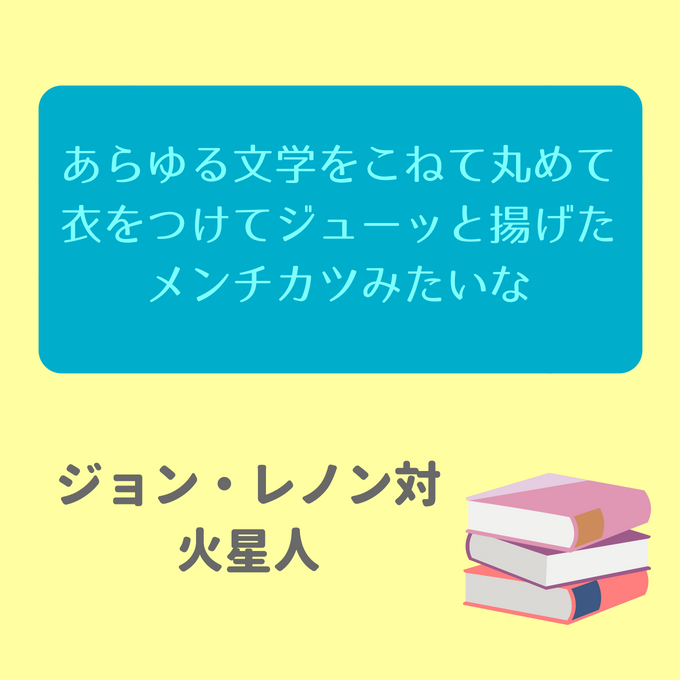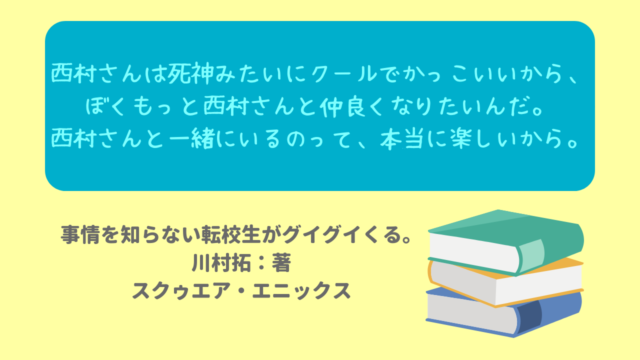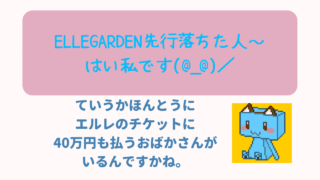新選組三部作
「新選組始末記」
「新選組遺聞」
「新選組物語」
子母澤寛:著
中公文庫
あらすじ
新選組研究の第一人者・子母澤寛が足を使って重ねた取材により、生き残りの隊士はじめ壬生屯所・八木家当主の子息、近藤勇の甥でのちに養子となる勇五郎氏、隊士たちの妻子や愛妾(当時、隊士たちは屯所から少し離れた場所へ愛人を住まわせ「休息所」と呼んでいた)などの貴重な証言が多数収録された文献。
また、新選組局長・近藤勇や副長・土方歳三、ほか隊士たちが遺した日記、手記、俳句など原文のまま掲載されており、当時の隊士たちの胸中を手に取るように読み取ることができる。
数多の人気作家たちが新選組を描く際の教科書となっている、新選組の真実を綴った最高峰古典。
ニャム評
新選組が好きな人にとっては「なにをいまさら」というべき、新選組伝記の元祖と位置づく本ですね。
私は新選組が大好きで、しかも司馬遼太郎の「燃えよ剣」から入ってしまったので、土方LOVE!歳三フォーエバー!的なファンなのですが笑、この「新選組の元祖本」というべき子母澤寛作品は手を出せずにいました。
なにしろ書かれた時期が古いので、難しくって読めないんです。
また、やはり司馬遼太郎、浅田次郎とエンタテインメント性の高い作品を読み進めてしまうと、小難しそうな子母澤寛の本に手を延ばす勇気がなかなか出ず・・・
今回、やっと読んでみようと思ったきっかけは、浅田次郎著「輪違屋糸里」でした。
糸里という名の天神(京都の芸妓)と土方歳三が物語の中心となっていて、新選組結成当初の局長である芹沢鴨暗殺を描く物語です。
芹沢鴨は創作物語ではことごとく乱暴者の嫌われ者として扱われているのですが、この「輪違屋糸里」では好感の持てる志士として生き生きと描かれていて、俄然芹沢鴨に興味を持ちました。
この本を執筆するにあたって浅田氏が子母澤寛の新選組三部作を重用していることを知り、芹沢鴨という人物についての文献を求めて手に取った次第です。
新選組始末記
三部作の1巻目となるこの本は、とにかく史実盛りだくさん、当時のことがかなりリアルに綴られています。
土方歳三の姉が嫁いだ佐藤家へ近藤勇がまめに送った手紙の内容や、隊士たちの俳句や日記などが原文のまま記載されています。
しかしこの原文がひどく難しくて読めないこと読めないこと。
非常に貴重な文献なので読みたいのはやまやまですが、漢文のような原文を読み解いているといつまでたっても読了できないので、途中であきらめてなんとなくながめる程度に読みました汗。
近藤勇が佐藤彦五郎氏へ宛てた手紙はしばしば登場し、京都で新選組がどのような活躍をしているのかをつぶさに報告している様子や、近藤の道場や妻子を面倒見てもらっていることへの礼などが複数回にわたり綴られていて、近藤の生真面目さがよくわかります。
また、「池田屋事件」で起きたことを詳細に報告しており、当時の史料としても貴重なものです。
なかでも私が注目したのは土方の句です。
なんと恋の歌を綴った句が残っていたそうで、
しれば迷ひしなければ迷はぬ恋の道
この句に縦三本の線を引いて消した跡があったそうです。
誰もが「非常にいい男であった」と語り残す土方歳三の、真の人物像が垣間見える史料であると思います。
しかしまあ本当に、写真を見てもいい男ですが、なにしろ女にもてまくったことでしょうね。
生きて動いている土方をぜひ見てみたかったものです。
子母澤寛という人は、新聞記者時代に培った取材スキルを活かして日本中を取材して歩き、足で稼いだ証言を自身の著書としたそうです。
主に幕末江戸の物語を綴り続け、大衆文学の草分けともいわれます。
その執筆活動の原点となるのは、祖父の梅谷十次郎(通称斎藤鉄五郎)に起因しています。
祖父の十次郎は彰義隊として上野戦争に参加し、惨めな敗戦を経験しました。
敗走して函館の五稜郭まで行ったものの囚われの身となり、そこで士籍を返還して札幌付近の開墾事業に従事、その後厚田村へと移り住んだそうです。
祖父の惨めな記憶を寝物語に聞いて育った子母澤寛が、幕末の動乱で散っていった命の物語をやがて紡ぐようになったのは必然だったのだろうと、彼の作家としての軌跡を本書巻末の解説で紹介されています。
文芸評論家の尾崎秀樹氏が手がけている解説も「解説とはかくあらん」とばかりの充実した内容で読みごたえがあります。
新選組遺聞
「始末記」に続く2巻目では、前作と同様に生存した隊士や壬生で関係のあった人々の証言や文書の記録などを紹介しています。
この本では新選組隊士たちの日常の言動などが多く記され、その人となりが伺える記述が多いことに目を引かれます。
芹沢鴨の逸話として面白いのが、松原烏丸因幡薬師に虎の見世物が来たときの話です。
虎のほかにインコやオウムなど色とりどりな生き物を披露しているというので大変な評判になったそうですが、「あれは人間が虎の皮をかぶっているのだ」とか「珍しい鳥はみんな染め物だ」などという噂が立ったので、それを聞いた芹沢が「その虎の皮をかぶっている奴を痛めつけてやる」と言い、ほかの隊士を引き連れて見世物へ出かけていったそうです。
これを聞いた八木家当主の子息・為三郎氏は面白そうだと思ってついていったところ、芹沢は虎の檻の前に立つと脇差を抜いていきなり虎の鼻先へ突き出しました。
芹沢はその見世物小屋へずかずか入ると、いきなりその虎の檻の前へ行って、脇差を抜くと、虎の鼻先へ、突き出しました。
みんなが、「わっ」といって、おどろき騒ぐと同時に、虎は物凄い声で、うおう・・・と耳もさけるように吠えて、芹沢をにらみつけました。
芹沢も少し吃驚した様子で、脇差をぱちんと鞘へ納めると、「これア本物だよ」 と、苦笑いをして引き揚げたことがありました。
対人間には向かうところ敵なしの芹沢も、本物の動物相手ではどうしようもないというのがなんともおかしい話です。
また、京都壬生の屯所としていた八木家を出る際、土方が八木家当主の源之丞氏へあいさつしたという場面では以下のようなやりとりがあったそうです。
おかしいのは、私の家に、「ながなが御部屋を拝借した寸志です」といって土方がうやうやしく奉書包みを出したのです。
父は、「お互に御国の為めですから」といって、辞退しましたが、とにかく受けねばならぬことになって、後で開いてみると金子が五両です。
これも後で聞いたのですが前川さんへは十両。
父はニコニコして、「二年も三年もいた家賃にしては安いなア」などと笑談をいい、そのまま、こも冠りの酒樽を幾つか買って、すぐに、お祝いだといってお届けしました。
沖田総司が相変らずのさのさして無駄口をきいて歩いていましたが、父の顔を見ると「八木さん、先生がどうも顔から火が出るっていっていましたぜ」と、愉快そうに笑っていました。
八木家と前川家は新選組の生活すべてを賄ってきたので、大変な苦労であったでしょうが、それだけ近くで共に過ごしてきたために隊士たちへの情も人一倍あったそうです。
振り返るといい思い出ばかりが残るといいますが、新選組と関わりを持った人たちの証言はみな、隊士たちへの愛や優しさが伝わってくるような微笑ましいものが多いです。
殺人集団とか壬生浪などと悪く言われていた新選組ですが、もとは百姓の家で育った二男三男坊や武家の部屋住みなどの集まりなので、よく気が利いて働き者であったといい、「ひとりひとりはじつに気持ちのいい青年たちだった」と異口同音に語られる証言が数多く見られます。
また、この本ではついに剣士沖田総司の最期について紹介しています。
沖田総司の最期についてはいろいろ語られていますが、「黒猫を斬ろうとしたが斬れなかった」という話がここにも出てきます。
「新選組始末記」でも沖田のひょうきんさがよく描かれていたので、死を目前にした頃の話はいっそう胸が詰まるような思いがしました。
近藤勇はこと人情に厚い人だったようで、隊士を非常にかわいがっていたそうです。
沖田を見舞った時の話は読者の涙を誘います。
この林太郎と、姉とに介抱されながら、天才剣士沖田総司が離れ座敷で病みぼうけて死んだのは、慶応四年(明治元年)六月十二日の夕方六ツ時頃(午後六時)で、この日の朝はいいお天気だったので、杖を持って、庭の中をぶらぶら歩いたりしていたが、昼頃から急変してそのままになった。
師匠の近藤勇が、甲陽鎮撫隊を率いて、江戸を出発したのは、この三月一日。その二日前の二月二十八日、忙しい最中を勇は夜更けて、沖田の離れ座敷へ駕籠を飛ばせて別れにやって来た。そして、
「骨と皮ばかりの総司の顔を見たら、俺はどういうものか涙が出て涙が出て堪らなかったよ」
と、後で、廿騎町へ帰って来てから、しみじみつね女に話していた。
この夜は沖田も声を出して泣いた。
注:このときすでに新選組は「甲陽鎮撫隊」と名を改め、徳川幕府の最後の戦いへと突入していました
新選組物語
いよいよ最終巻となるこの本では、新選組の最期を多角的に切り取った逸話が多く記されています。
また、この巻でのみ、子母澤さんが聞き集めてきた話を物語として創作している短編がいくつかあり、その物語が秀逸です。
ここまで難しい旧仮名を四苦八苦しながら読んできたごほうびみたいにうれしかったです笑
「かしく女郎」という短編では、鳥羽伏見の戦いで敗走し、富士山艦という船で品川沖から江戸へ逃げ戻った隊士たちが気晴らしに深川の仮宅(洲崎)へ繰り出した話です。
品川楼という廓(くるわ)で大騒ぎしていると、「かしく」という芸者だけが一滴も酒を飲んでいない。
「我々の杯を受けられぬか」と隊士たちは気色ばみますが、聞くとかしくは酒が入ると大変な乱暴を働くということで、お座敷での飲酒は厳禁なのだといいます。
とたんに面白がった隊士たちはかしくに浴びるほど酒を飲ませ、かしくの罵詈雑言を面白おかしく酒の肴にして大盛り上がりしました。
その翌日、永倉新八がぶらりと近辺を散歩していると、近在の若い剣士に絡まれて剣の立ち合いが始まってしまいます。
剣士たちをたちまち斬り下げ、そのまま廓へ戻った永倉を見たかしくは「刀が汚れたでしょう」と言って永倉の刀をきれいに拭い、打粉をしました。
驚く永倉たちに、かしくは身の上を語り始めます。
もとは弘前藩の足軽の娘であったが、父の剣の腕前に嫉妬したある者が父を殺してしまった。
その後病弱の母も亡くなり、家の借財のため長女がかしくと名乗り女郎と成り果てた、というのです。
父の仇討ちを胸に秘して生きてきたというしんみりした物語ですが、この思い出を語る永倉自身の言葉もまた、新選組の終焉が見えていてもの悲しさが募ります。
もう自分達の行先きの山も見えた、今日あって明日はない命のような気がしてならなかった。何んとなく果敢ない気持だ。今にして考えると、この頃は、どうにかして、この淋しさを忘れたい--そんな風でした。
落ち目になるとこれまでの同志の離合集散、或は暗殺され、或は断首され、或は死を賭して脱走するというような事柄が、眼の前にはっきり浮かんで来て、堪らなかった。
永倉新八翁遺談
この巻のちょうどまんなかから「新選組」と題した物語が始まります。
いよいよ鳥羽伏見、戊辰戦争と負け戦を続けてきた新選組と近藤勇の最期が描かれていきます。
この物語では近藤が「新選組局長」の目的を捨て、「上石原の道場主の近藤勇」として命を終えたいと希望する悲しみの旅路となっていきます。
新選組は「甲陽鎮撫隊」と名を改め、新たな隊士を募るため江戸から甲州街道を下っていきました。
途中で近藤の故郷・上石原(いまの調布市)を通ると、道には知った顔が土下座をして平伏しています。
土方は誰彼にも会釈し、それを見た人々は涙ぐんだといいます。
ここで懐かしい人たちに顔を見せることを拒む近藤の心情は、村から連れだった者たちがすでにこの世を去り、故郷の人たちに合わせる顔がないというものでした。
そしてまた、故郷を見ることで「個人の近藤勇」の心に戻ってしまうことを恐れ、かたくなに人々の前に出ようとしないのでした。
この後、死に場所を求めるように戦いを続ける土方は足を止めることなく戦地へと向かい続けます。
一方で「局長」であることに疲れ切った近藤は千葉の流山で官軍へ降り、その後板橋の刑場で斬首されました。
下総流山の逗留は「会津藩へ合流するための中継地」とされていましたが、千葉県流山市のホームページによると、昭和50年に新たな文書が発見されて新選組(甲陽鎮撫隊)の動向が明らかになったとのことです。
本作の初版は1977年ですが、執筆されたのはそれ以前なので、このあたりの記述は現在の解釈とは変わっているかもしれません。
流山市のホームページはわかりやすい説明が載っていておすすめです。
とうとう最後となる、近藤が流山で薩摩藩士の有馬藤太に連れられて行くシーンでは、有馬が近藤の心に触れ、その命を惜しんで落涙する場面が目に浮かぶように描かれています。
「有馬さん。私は、さっき、一寸の暇に、辞世を書きました。御覧下さいますか」
「拝見申そう」
有馬は、馬の首を寄せた。
近藤は、ふところから、懐紙へ書いた詩稿を出した。
「百姓出で、無学ですからお恥かしいのですが--」
「いや、近藤どん、有馬藤太、おはんのような立派な武士の辞世の詠を、第一に拝見申す、面目でごわす」
「恐縮です」
有馬は渡された詩を、まじまじと見ていた。そして、やがて、
「孤軍援ヲ絶ッテ俘囚ヲ作ル、顧テ君恩ヲ念へバ涙更ニ流ル--一片ノ丹波、能ク節ニ殉ズ--」
有馬の力強い太い声は、野から野へ響いた。しかも、詩の半にして声は涙に代って、
「近藤どん、おいは、おいは--武士が忌やになり申したッ」
がッばと、鞍へ伏せて終った。
近藤は、はじめて、湧くように涙が出て来た。
新選組とはいったいなんだったのか?
その解答は個々人の心にそれぞれ見つかるものです。
この本にはその解答を得る鍵が隠されています。
日本の歴史的人物を追うといつも最後は悲しみ、さみしさが伴うのですが、日本史に名を連ねた傑士たちはみなどこかに敗者の影を内包していて、平安時代に絶大な権力を掌握した豪傑・平清盛でさえも、その人生の終幕にはわびしさが漂っていました。
これは日本の土着的なものなのか、どうも欧米のような全能感やパリピ的な明るさがありません。
まさに「平家物語」の冒頭の
祇園精舍の鐘の声、諸行無常の響きあり。娑羅双樹の花の色、 盛者必衰の理をあらはす。奢れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者もつひにはほろびぬ、ひとへに風 の前の塵に同じ。
ということなのかもしれません。
しかし、その傑士たちの影を見つめるなかに、日本人の心のひだに触れるような共感や感動がたしかに見つけられます。
人はなぜ、なんのために戦うのか。突き詰めれば栄誉や金銭、名声だけではない、大切な理由がそこにはありました。
それを人は“大儀”と呼ぶのかもしれません。
その意義をくみ取れたとき、人間として生きる意味を改めて知ったような感動を得ることができるから、私たちは飽きもせず読み続けるのでしょうか。