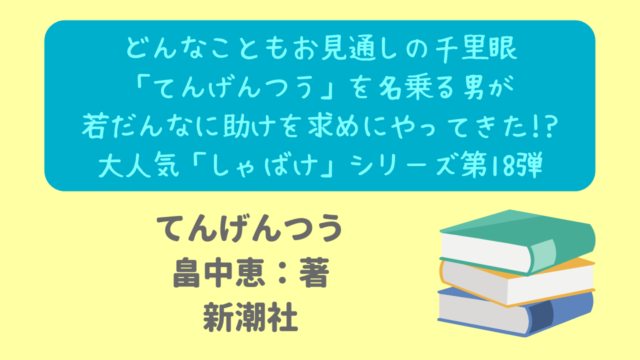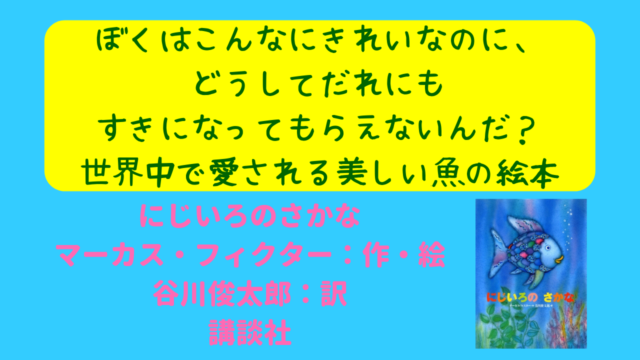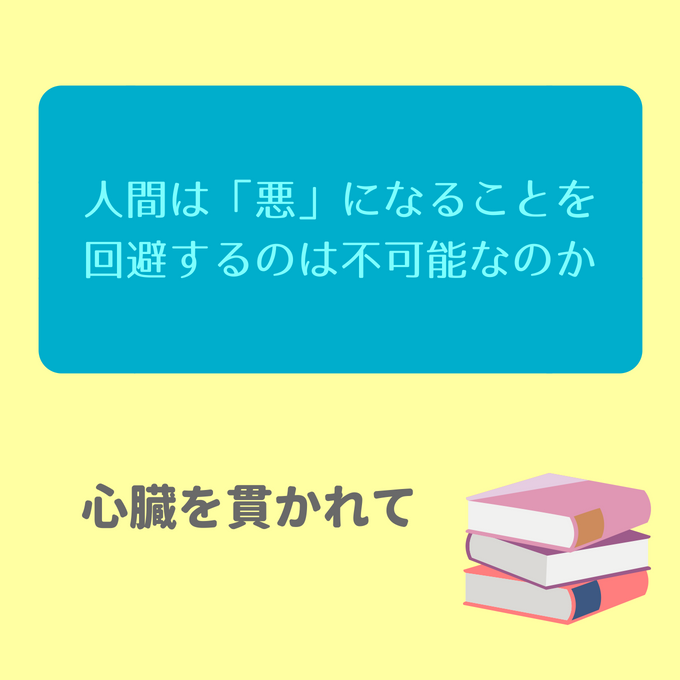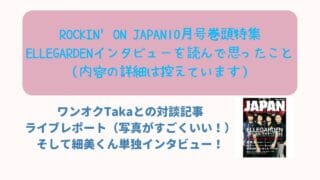決定版 日本のいちばん長い日
半藤一利:著
文藝春秋
あらすじ
昭和20年8月15日正午、ポツダム宣言受諾が天皇自らの声によって全国民に伝えられた。
ラジオ放送を通じて日本中に流れたその声は、前日の夜にレコード盤に記録された録音である。
この玉音放送が現実世界の空気を震わせるまでには、じつに多くの混乱と恐慌が生じた。
ポツダム宣言を受け入れるのかどうか、鈴木貫太郎総理率いる内閣は紛糾。
一刻も早くポツダム宣言受諾を打電したい外務省と、あくまで「国体護持」に執着する陸軍省とで会議は決裂し、その間にも戦況は刻々と移ろい、ついに広島、長崎へ世界初の原子爆弾が投下される最悪の事態に。
こうして日だけが過ぎていき、ついに8月14日、鈴木首相は「ご聖断を拝する」として最高戦争指導会議に天皇を招いての「御前会議」を強行する。
一方、ポツダム宣言受諾により国体護持が不可能になると考えた陸軍の一部青年将校らは、あくまで徹底抗戦を蹶起しようと、天皇があらせられる御文庫の占拠を企てる。
全国民へ戦争が終わることを自らの言葉で伝えようとする天皇とそれを支持する内閣、そして玉音放送を阻止しようと反逆行為に走る将校たちの間で緊迫した時間が流れ始めた--。
8月14日正午から24時間に起きた出来事を、一時間ごとに項を立てて物語は進んでゆく。
本書のプロローグには下記のように綴られている。
文藝春秋の<戦史研究会>の人々が『日本のいちばん長い日』を企画し、手に入る限りの事実を収集し、これを構成した。
いわばこれは「二十四時間の維新」である。しかもそれは主として国民大衆の目の届かないところでおこなわれた。(中略)
いままで埋もれていた資料をもとに、日本人の精神構造を主題にして構成した、二十四幕の「長篇ドラマ」なのである。
24時間の間に皇居ならびに御文庫周辺で起きた、ポツダム宣言受諾から玉音放送が流れるまでの物語を、膨大な資料をもとに組み立てたノンフィクションドラマ。
ニャム評
初版は1965年という超ロングセラー本です。
これは、敗戦経験のなかった「常勝帝国」が初めて負けを認めなければならなくなった、その瞬間の物語です。
時の首相、鈴木貫太郎率いる内閣及び、昭和天皇がポツダム宣言を受け入れるまでの葛藤と、それを受け入れられずに反逆行動を取った一部将校のクーデター計画が一時間ごとに語られていきます。
「ポツダム宣言」とか「御文庫」とか「国体護持」とか言われてもサッパリという方でも、「玉音放送」は聞いたことがあるのではないでしょうか。
天皇自らが文書を読み上げる声を録音し、8月15日に放送したことで実質的に「終戦」と位置付けられています。
ポツダム宣言とは、アメリカ、イギリス、中国が日本に対し無条件降伏するよう求めた宣言です。
この「無条件降伏」とは具体的になにを指すのか、ここで内閣は紛糾しました。
国体は護持されるのか、この一点が会議の最大の争点となりました。
国体護持とは、「天皇を中心とした秩序」とのことで、ざっくり言うと「天皇主体による政治」というようなことです。
ポツダム宣言により、天皇制は廃止され、日本国はアメリカ合衆国と国名を変更されると陸軍は危惧していました。
実際には、アメリカ政府は「日本人から天皇を奪ったらなにをしでかすかわからない」と懸念し、天皇制は廃止せず「象徴としての天皇制」を残したのですが、とにかくこの時には「陛下の命が奪われるのでは」と最悪の想像が働いたわけです。
国民にこれ以上の苦しみを負わせるわけにはいかないと心を痛めていた昭和天皇は
「ともかく、これで戦争をやめる見通しがついたわけだね。それだけでもよしとしなければならないと思う」
とお気持ちを語り、また「国体護持は守られる」という確信を持って内閣へ語りました。
こうしてポツダム宣言を全面的に受諾することが決定し、日本は戦争を終わらせると決まりました。
ところがこれを受け入れられなかったのは陸軍です。
「勝つまで戦いはやめない」と日本国の勝利を信じていた将校たちは、玉音放送の前に無条件降伏を知らされますが、それは臆病な内閣が楽をしたいという甘えだといきり立ちます。
それでもほとんどの将校たちが無念を腹に飲み込んでいたなかで、数名の将校がクーデターを起こします。
ポツダム宣言受諾を全国民に伝える前に天皇を擁し、本土決戦へ持ち込もうと考えたのです。
将校たちは皇居へ向かい、そこにいた侍従たちや、天皇の声を録音し終わった放送員たちを拘束し、狭い一室へ軟禁します。
さらに近衛師団長を殺害し、ニセの師団長命令を作成し発布します。
それは「国体護持のために玉音放送を阻止し、皇居を占拠せよ」という内容でした。
銃剣を持った兵士たちが皇居へ押し寄せ、天皇側近たちは命を奪われる危機にさらされ、天皇の起居する御文庫の目前まで暴力が押し寄せようとします。
終戦前夜にこれほど大がかりなクーデターが起きようとしていたことは知りませんでした。
また、二度の原子爆弾が投下され、瀕死となった日本で、陸軍だけが力を誇り、まだ戦えると信じて疑わなかったことにも驚きました。
どんだけKY・・・。
天皇の声を吹き込んだレコードが現存することは知っていましたが、そのレコードが取り上げられ破壊される危機に直面していたことなど、初めて知る事実が多く記されていました。
本書で目を引かれる記述は多くありましたが、なかでも天皇の言葉が重く心に響きます。
「わたし自身はいかになろうとも、私は国民の生命を助けたいと思う。(中略)
この際、わたしのできることはなんでもする。国民はいまなにも知らないでいるのだから定めて動揺すると思うが、私が国民に呼びかけることがよければいつでもマイクの前に立つ。陸海軍将兵はとくに動揺も大きく、陸海軍大臣は、その心持をなだめるのに、相当困難を感ずるであろうが、必要があれば、わたしはどこへでも出かけて親しく説きさとしてもよい」
と周囲に語られる場面は胸をしめつけられます。
また、御文庫まで兵が押し寄せつつあることを聞いたときには
「兵を庭へ集めるがよい。私がでていってじかに兵を諭そう。兵に私の心をいってきかせよう」
と侍従へ伝えました。
当時、天皇が民衆へ直接声をかけるということなどは畏れ多いことだったため、この言葉に侍従たちは泣きそうなほど感動し、頭を上げることができなかったそうです。
クーデターが未遂に終わり、それを藤田侍従長が報告した際には
「藤田、いったい、あのものたちは、どういうつもりであろう。この私の切ない気持が、どうして、あのものたちには、わからないのであろうか」
とつぶやかれたそうです。
先日も、昭和天皇に長く仕えた侍従の日記が出てきたことがニュースになっていました。
その日記では昭和天皇の嘆きがメモとして記録されており、この世を去るまで戦争責任に非常に敏感であり、苦悩を背負ってきたことがうかがえます。
昭和天皇侍従の日記 歴史を問い返す大切さ
2018.08.28
毎日新聞社説
太平洋戦争に関する著書は膨大にありますが、本書は長い戦争のなかでももっとも重要であった一日の濃厚な記録として、史実を伝える稀有な一冊であると感じました。
24時間の長い、長い戦いの記録は、現代を生きる日本人に問いを投げかけます。
命がけで終戦へと導いた日本の未来は、平和な国として再建しただろうか?と。