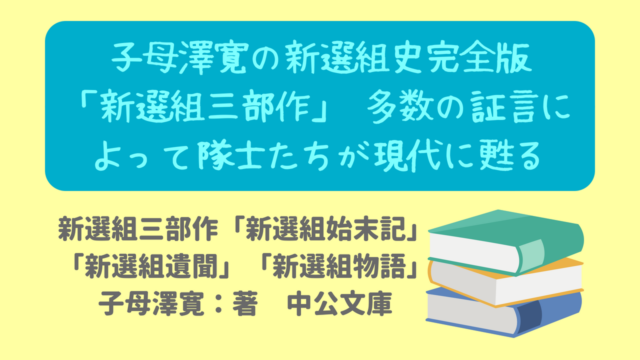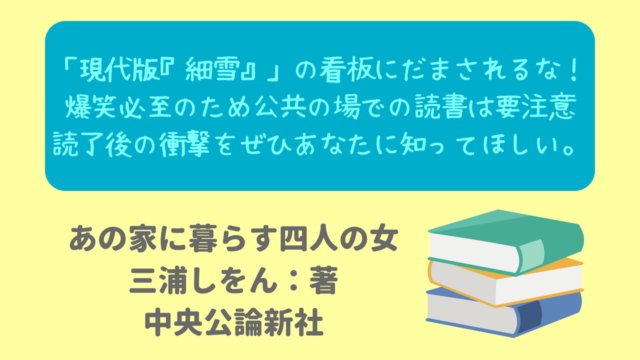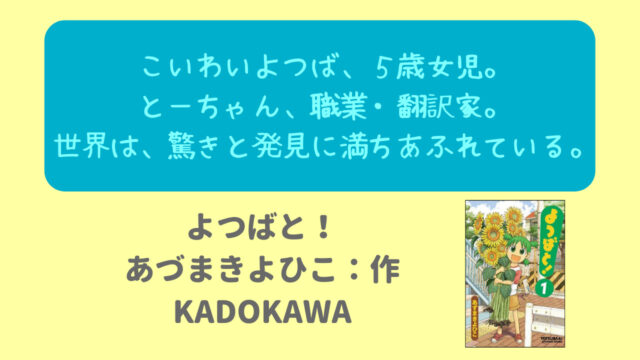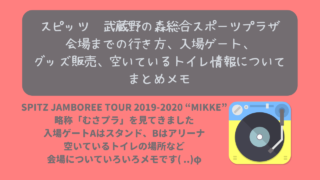妙麟
赤神諒:著
光文社
あらすじ
豊臣秀吉が天下統一に向けて躍進する一方、九州最大の勢力を誇っていた大友家は破滅の一途を辿っていた。
最後の大友家当主となった大友宗麟は島津家の侵攻を食い止められず、最後の砦である丹生島城が陥落目前となったなか、その前衛の地である鶴崎城で敵を蹴散らし島津軍を震撼させた将がいた。
その名は妙林尼(みょうりんに)。
すでに仏道に入った女性が、類まれな才知と豪胆さで巨軍を打ち倒すとは、いったい誰が予想しただろうかーー。
林左京亮(はやしさきょうのすけ)の娘、妙(たえ)は文武ともに秀でた勝気な女子であった。
14歳のある日、父の左京亮とともに上原館(うえのはるやかた)を訪れた妙は、見事な篠笛の音を耳にする。
桜の下で美しい音色を奏でていた若者に心を奪われた妙は、名も知らぬ青年と再会すべく来る日も来る日も探し続けた。
篠笛の君に出会えるやもと期待して軍師・角隈石宗(つのくませきそう)の塾にも通ったが、若者の姿を見つけることは適わず、妙の軍才に磨きがかかるだけであった。
一方、篠笛の名手である臼杵右京亮(うすきうきょうのすけ)もまた、桜の木の下で出会った少女を忘れられずにいた。
白拍子の母から生まれた右京亮は見目麗しく芸妓にも長けており、母の形見である篠笛は聴く者を魅了するほどの腕前であった。
そんな右京亮はしかし、幼い頃の不遇な境地から脱するべく、他者を足場にしてのし上がり、不安定な国内を操作して権力を手にしようと画策する反逆者でもあった。
宗麟の近習(※近習:きんじゅ 主君のそばに仕える者)として働き、宗麟の心をつかむためにキリシタンとなり、宗麟をそそのかして内乱を起こそうとしていたのだ。
ふたりが巡り合うことのないまま二年の時が過ぎた。
篠笛の君をとうとう諦めようと考えた妙と、自身の野望を一気に加速させようとする右京亮は、キリスト教教会のデウス堂前で思いがけない再会を果たす。
互いに惹かれ合うが、皮肉にも右京亮自身が仕組んだ悪略によってふたりが同じ道を進むことは適わなかった。
右京亮は自身の策謀から逃れられず、「キリシタン王国」という幻に絡めとられていく。
また、妙も右京亮の置かれた立場を知り、右京亮と夫婦になる夢は潰えたことを受け入れた。
そんな傷心の妙に寄り添い続けたのは、妙の命の恩人である吉岡覚之進であった。
右京亮と一緒にいたところを襲われ重傷を負った妙を手厚く介護し、右京亮が去ったあとも妙を見守り続ける覚之進の優しさにいつしか妙は心を寄せるようになり、やがて妙は吉岡家へ嫁ぐこととなる。
愛する伴侶を得て幸せな暮らしが訪れるはずだった妙の背後に、しかし不穏な影は少しずつ忍び寄っていた。
急激に勢力を拡大したキリシタン集団と大友家の家臣たちの間にあった軋轢は日ごと大きくなっていき、一触即発となっていた。
さらにその不安定な情勢につけ込むように、隣国の島津が大軍で攻め入ろうと押し寄せてきた。
九州一の大大名、大友家がついに滅びる瞬間は、刻一刻と迫っていたーー。
ニャム評
豊臣秀吉が天下統一を成し遂げる以前、九州一の勢力を誇っていた大友家。
その大友家を鮮やかな筆致で描き出す第一人者、赤神諒氏による「大友サーガ」最新刊は女の大将が主人公です。
妙林尼(みょうりんに)と名乗り、若くして仏門に帰依した尼僧は、林左京亮の娘であり、吉岡覚之進に嫁いだ妙という女性です。
この妙という人が、とにかくじっとしていない。
己の人生を自らの手で切り開き、どんな逆境にも屈することのない鋼の精神を持った女性なのです。
本書のプロローグは、クライマックスである島津軍との戦いの真っ只中。
すでに尼僧となった妙が、鶴崎城の城代として吉岡家の全軍を指揮し、疾風のごとき迅速さで島津の大軍を陥れていく様が描き出されます。
1ページ目から強力な引力で物語に引き込まれていく感覚は、妙というキャラクターの力技によるもので、とにかくグイグイと読み進めてしまいます。
林左京亮という厳格な父に育てられ、一本気で負けず嫌いの性格に育った妙は、文武ともに優れた秀才であり、「男に生まれていれば」と惜しまれる軍才を持つ少女でした。
そんな妙が持たなかったのは、音楽の才能です。
音を奏でることは大好きで、熱心に練習するものの、「下手の横好き」を自認する腕前でした。
そんな妙がある日、篠笛の達人と偶然出会います。
臼杵右京亮をひと目見て恋に落ちた妙は、さっそく「篠笛の君」と再開すべく行動を開始します。
名のある家の若者であろうと当たりをつけ、年頃の男子がみな通った角隈石宗の塾へ自身も通い、首にかけていたクルス(十字架)を見てキリスト教会へも足繁く通い、さらに府内(豊後の国府、中心地)を探し回ります。
いまの時代で言えばプチストーカーですが笑、戦国の世ではこうでもしなければ会いたい人に会うことすらままならなかったのでしょう。
こうして2年もの間探し続けますが、篠笛の君と再び会うことは叶いませんでした。
その後、なんやかやとありまして(そこは本書をお楽しみください)、妙は吉岡覚之進のもとへ嫁ぎ、鶴崎城へ居住することになります。
やっと幸せを手に入れたかと思いきや、ここでは壮絶な嫁姑バトルが勃発するのです。
「渡る世間は鬼ばかり」の赤木春恵さんもビックリの、嫁いびりの域を超えた悪意が妙に向けられるのですが、その仕打ちがひどい。
姑であり覚之進の母でもある法歓院は、家柄の低い林左京亮の娘である妙を見下し、さらに右京亮との過去に悪印象を持っているため、嫁としてやってきた妙を快く迎え入れることができませんでした。
妙を家から追い出さんと、法歓院は家来とともに様々な手を尽くして嫌がらせの限りを尽くします。
吉岡家の大事な行事を妙に伝えない。
覚之進からの文を妙に渡さない。
城の中でも粗末で寒い部屋を与える。
妙と侍女の萩に食事を出さない。
さらには勝手に妙の部屋へ入り、嫁入り道具として持ち込んだ着物や金子まで持ち去るようになります。
嫌がらせを超えて、これでは窃盗ではないかと呆れるほどの悪事を矢のごとく降らせます。
普通の女性なら精神が参ってしまうような仕打ちを受け続け、その悪意を妙がどのように切り抜けるかというのが、じつはこの物語のもっとも重要な一場面ではないかと私は思っています。
法歓院のいじわるな心は周囲の者にも伝播し、覚之進と前妻との間に生まれた男の子である甚吉も後妻の妙をばかにするようになります。
そんな四面楚歌でも、妙は侍女の萩にこう言います。
「萩、私は決めたぞ。府内で覚之進さまはお国のために粉骨砕身尽くしておられる。吉岡家の嫁姑のつまらぬいさかいなど、お耳に入れるべきではない。私は鶴崎で、私の戦いをする」
妙は法歓院の仕打ちについて文で伝えようと考えていた。だが、親孝行者の覚之進が法歓院と妙の関係を知れば、心を痛めるだけだ。無用の心労をかけるべきではない。たとえ覚之進が法歓院を捨てて妙を選んだとしても、それは何の勝利も意味しない。夫から母を奪って喜ぶ妻は間違っている。それに、妙は甚吉の母となったのだ。鶴崎にあって、わが子を育てねばならない。逃げ出すわけにはいかないのだ。
「第七章 恋を奏で、愛を唄わん」218ページより引用
これは世の女性すべてが心に刻むべき一文ではないかと思います。
いやほんとに。
義母との確執は日本のみに留まらず、世界中で勃発していますが、食べ物もルールも笑いのツボも違う環境で長く暮らしてきた他人同士が突然家族になるんですから、ぎくしゃくしたりかみ合わないことがあるのは当然です。
ましてあちら様(義母側)は年齢を重ねてきたぶん、若い嫁の至らなさが目につくのは当たり前。
法歓院はやりすぎですが、やはり若輩者としては年長者を多少立てる気持ちを持って接するのが穏当だろうと思いますし、大切な配偶者の親であれば配偶者と同じように大切にすべきでしょう。
妙のように強い心でいるのは難しいことですが、人を大切にするということを忘れてはいけないと改めて気づかされる一文でした。
「大友サーガ」のなかでも大友家が終わりを迎える頃が舞台となっているので、どうしても物語の随所に悲しみ、侘しさの片鱗が漂っているように感じながら読み進めました。
歴史小説のなかでもとくに戦国時代の物語は悲しい結末であることが多く、本当はあまり好きじゃないんですよね。笑
それでも読むのをやめられないのは、人間が人生のすべてをかけて必死に生きた姿を見ることができるからではないかと思います。
「必死に生きる」という経験をすることがほとんどない現代で、歴史小説は私たちの知らない人間の奥深さを教えてくれるのです。
戦神
赤神諒:著
大友家最強の武将・戸次鑑連は母の腹を割いて生まれた「鬼の子」だった――
「戦神」と恐れ崇められた鑑連と妻・お道の愛を描いた「大友サーガ」ファン垂涎の物語