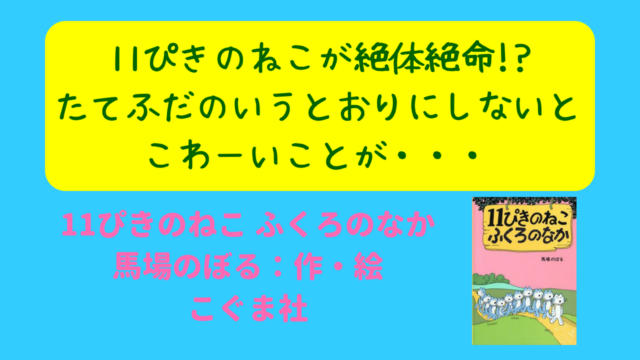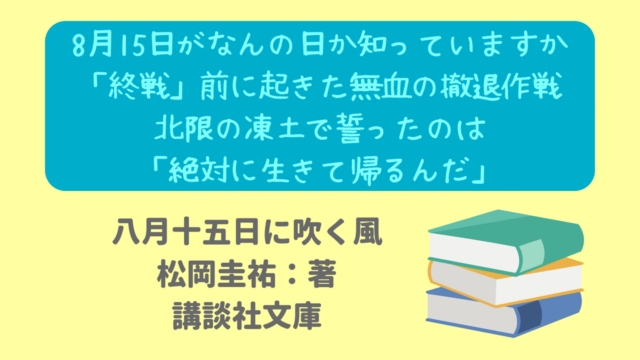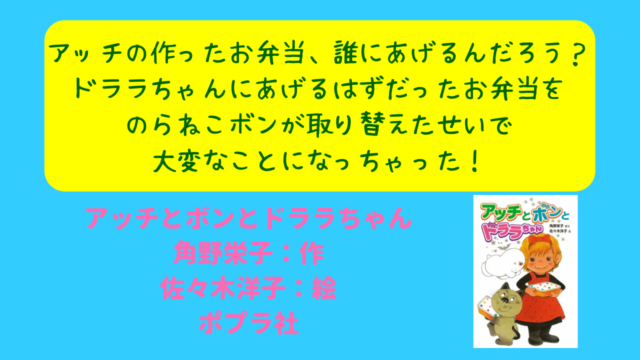友罪
薬丸岳
集英社文庫
あらすじ
※実際に起きた少年犯罪をヒントに描かれた物語であり、物語の軸が「友人が殺人犯だったらどうするか」という内容であるため、記事内で一部ネタバレに触れています。
益田はジャーナリストを志す27歳の青年。
編集職希望で働き口を探すが、無職で就職活動を続けるうち貯金が底を尽き、家賃未納でアパートを追い出されてしまう。
やっとのことで見つけた仕事は、寮付きのステンレス加工会社だった。
益田がステンレス加工会社で働き始めた同じ日、鈴木という青年も寮に住み込みで入社していた。
益田と同い年だという鈴木は陰鬱で近寄りがたく、ほかの従業員とも馴染めずにいたが、次第に打ち解けるようになっていく。
ある日、鈴木は益田にこんな質問をする。
ーー僕がもし自殺したら、悲しいと思う?
悲しいに決まってるだろう、と答えた益田に、鈴木は友情を感じ、心を開いていく。
一方、益田は14年前に起きた殺人事件について調べていた。
「黒蛇神(こくじゃしん)事件」と俗に呼ばれる、14歳の男子中学生が小学校低学年の児童2名を殺害した事件。
その残虐な殺害方法や、「黒蛇神」と男子中学生が妄想のなかで作り上げた神へ「生贄として捧げる」と記した手紙があったことから世間を震撼させた。
その事件を追ううちに、益田は妙な感覚をおぼえるようになる。
犯行当時、未成年だった14歳の中学生は、もしかして身近にいる彼ではないのかーー。
友人が大罪を犯した人間だったとしたら、あなたはそれでも友人としてそばにいられるだろうか。
人間の心の奥底にある闇と光にフォーカスを当てた話題作。
ニャム評
もしも友人が殺人犯だったらーー。
そこを発端に、たくさんの人を巻き込みながら物語は進んでいきます。
主人公の益田は、「自分の記事で人を救いたい」という思いでジャーナリストを目指していましたが、職に就けずしかたなしに寮つきの工場で働くことになります。
同じ日に入社した同い年の青年・鈴木とは最初の印象が悪かったものの、次第に打ち解けるようになっていきます。
そんななか、あることをきっかけに益田は鈴木が有名な殺人犯なのではと思い始めます。
鈴木の現在の姿を紹介する記事を書けば、記者としての仕事を得られるかもしれない。
その思いにとらわれた益田は、大学の先輩が勤める週刊誌に記事を寄稿しようと考えるのですが、それはつまり友人の鈴木を売ることでもあります。
個人的な感想としては、益田が鈴木を「友人」と思うほど心を開いていないように感じたので、「友人が殺人犯だったら」という悩みを抱えているようには読み取れませんでした。
それよりも、償いきれないような大きな罪を犯した人間が、社会のなかでどう生きていくのか、それを知ったとき、周囲の人間はどのように反応するのか、そして自分自身はその相手とどのように接していくのか、そういったそれぞれの心の動きをリアルに描き出している点が印象的でした。
益田はジャーナリストとして世間に「真実」を伝えていきたい、という夢を持っていますが、それは並行して「認められたい」という承認欲求でもあるように感じます。
自分はものすごい特ダネを持っている。
それを原稿にすれば大金はもちろん、希望の職も、そして名声や羨望を手にすることもできる。
しかし、それを記事にすれば、鈴木は職も住む場所も、そして現在の名前もすべて失うことになります。
もしかすると、命までも失うかもしれない。
「僕がもし自殺したら、悲しいと思う?」
鈴木に問いかけられた益田は、苦い過去を思い出します。
益田は中学生のときに同級生を自殺で亡くしていました。
鈴木が「黒蛇神事件」の犯人だと公表すれば、鈴木は自ら命を絶ってしまうかもしれない。
特ダネを売りたい気持ちと、鈴木という友人を売っていいのかという後ろめたさに揺れる益田の葛藤がどのような結末を生むのか。
こういった物語を読むと、「自分だったらどうするだろう」と立場を置き換えて考えてしまいます。
これはあくまで私見ですが、一般的に罪を犯した者は法によって裁かれるものであり、個人の人間によって裁かれればそれは私刑(リンチ)になってしまいます。
本書を読めばすぐに思い出されるのが、「神戸連続児童殺傷事件」です。
殺害犯の少年は犯行当時14歳で未成年だったため、実刑にはならず更生施設へ入所することになりました。
この物語のなかでは、その実際の事件と酷似した事件が登場し、犯行に及んだ元少年について様々な人の声が描かれます。
同じ空気を吸うのもいやだ。
不幸な人生を歩んでいてもらいたい。
犯人があいつだって知ってたらボコボコにしてやったのに。
加害者が幸せを手にすることを許さない、それが「世間」の感情です。
しかし、先述しましたが、罪を裁くのは法であり、個人ではありません。
現行法に則ってその罪と向き合った人は、定められた刑期を終えれば、それについて咎められることはないはずです。
もしも重罪を犯した元犯人だとしても、法に準じた贖罪を終えていれば、まったくの赤の他人からとやかく言われる筋合いはないし、ましてや嫌がらせや暴行などを加えればその人が加害者として罪を負うことになります。
日本にいると、この「世間の感情」という勘違いが顕著であり、しかもまかり通ると信じている人が多数いると強く感じます。
一度罪を犯したら、二度と許されない。
誰に許されないのか?
「世間」に。
では、「世間」とはいったいなんだろうと思います。
「黒蛇神事件」の犯人について原稿を書いたものの、彼を誹謗する内容ではなかったことで、益田は大学の先輩になじられます。
週刊誌が欲しているのは「真実」ではなく、「あの凶悪犯はいまでも危険人物である」と思わせるような「ネタ」なのです。
益田の先輩はこう言います。
「奴には世間に語る義務があるんだ。自分がやったどうしようもない罪深い行為について。そしてそれを知りえるおまえにもそのことを伝える使命があるんだ。わかったか!」
これは正確には正しくありません。
益田の先輩の本音は、
「世間の人が期待する、『やっぱり凶悪犯はいまでも凶悪だ』というネタをよこせ」
なのです。
話は飛びますが、「新潮45」で頭のおかしい議員が寄稿した内容や、さらにそれを助長するような寄稿文が大きな批判と話題を集めましたが、週刊誌は「悪者をつるし上げて、それをみんなでこき下ろす」ことで雑誌が売れると信じています。
「人は、誰かの悪口を言いたいから、それを正当化するきっかけを作れば売れる」と思い込んでいます。
だから、悪者を作り出すのです。
当然ながら、この物語のなかの殺害犯の元少年に、「世間に語る義務」などあるはずがありません。
どんな義務だよ、と読みながら心の中で突っ込みました。
彼らの言う「義務」は、たとえば芸能人が不祥事を起こしたときに謝罪を求めるのと同じです。
芸能人が有名だからって、なぜ「お茶の間」に謝罪する必要があるのか、個人的にはまったく理解できません。
もともとワイドショーはきらいですが、そういった話題になると本当にうんざりします。
なので、テレビ誌の記者を辞めてからはほとんどテレビを見なくなりました。
物語のラストは、登場人物が苦しみながらも、悩みぬいた末に出した「正解」が描かれます。
その「正解」はちょっときれいすぎるかなと個人的には思いましたが、物語としては読後感が悪いまま終わらなくてよかったと思うような幕引きでした。
しかし改めて、日本人特有の「自分と少しでも違う者は徹底的に排除する」という空気を認識させられるような、重苦しい物語でもありました。
私の言っていることはたぶんきれいごとで、実際に自分や身近にいる大切な人が被害者になったらどうだろうと考えると、恐怖と憎しみに絡めとられてしまうだろうと思います。
それでも、犯罪者は死ぬまで不幸でいなければならないなどと思うことは異常ですし、「おまえもそう思うだろう?」という同調圧力が恐ろしいと感じます。
罪を憎んで人を憎まず。
言うは易く行うは難し、ですが、考えることを放棄してはいけないことだろうと思っています。
まあとにかく、突っ込みどころも満載でしたが、考えさせられることも非常に多い作品でした。
生田斗真と瑛太による映画化もされ、話題となりました。
本編は見ていませんが、予告を見た限りでは原作と少し筋が違うようです。
映画よりはこの原作本のほうが青臭いというか、青春っぽさがあると感じます。
映画は「64 ロクヨン」を制作した瀬々敬久監督が手掛けており、かなり社会派な色が強調されていました。
草野マサムネ、古市コータロー、TOSHI-LOW、岡村靖幸、武内亨らの“14歳”がここにある。
14歳 fourteen
後藤正文、川上洋平、尾崎世界観、増子直純、細美武士らの“14歳”がここにある。
14歳 fourteen Ⅱ
宮藤官九郎、宇多丸、田中和将、TAKUMA、甲本ヒロトらの“14歳”がここにある。
14歳 fourteen Ⅲ