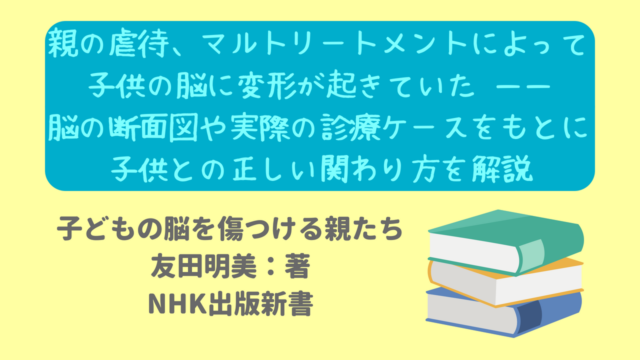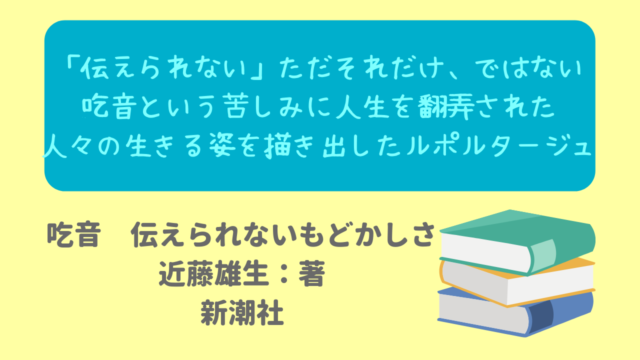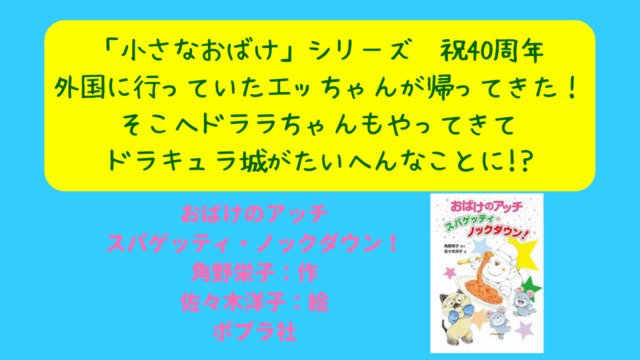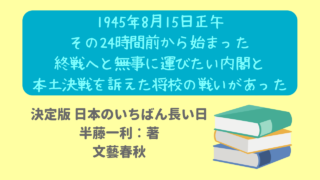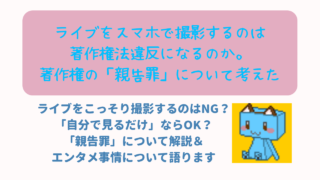風の歌を聴け
村上春樹:著
講談社文庫
あらすじ
1970年8月。
東京の大学に通う「僕」は、夏休みに実家へ帰省していた。
友人の「鼠」となじみのバーでひと夏かけてプール一杯ぶんのビールを飲み、くだらない話をして過ごした。
ある日、「僕」がジェイズ・バーでいつものようにビールを飲み、洗面所へ行くと、左手が4本指の女の子が転がっていた…。
ニャム評
解説無用、日本人作家でもっとも有名なデビュー作のひとつといえる本作品は、村上さんが生まれて初めて書いた小説です。
彼のエッセイなどでよく見かける有名なエピソードとして「神宮球場でデーゲームを見ていたときに、『小説を書いてみよう』と思い立った」というものがあります。
当時、ジャズ・バーを経営していた彼は、店を閉めたあとの台所でコツコツと書き進めたそうです。
これまで習作らしいものもいっさい書いたことがなく、初めて書いた小説がこれだとは、執筆スキルの高さに驚愕します。
が、それから数十年が経ち、これまでに生み出された作品をひも解くと、作家の素質がもともと備わっていた人なのだろうと思わされます。
この美しく完成された作品が処女作というのは、並みの文筆家とはスタートから違うんだなと。
村上さんの本は大好きですが、刊行された書物のうち半分くらいしか読んでおらず、さらに初期の作品は「羊をめぐる冒険」でつまづいてしまい、これまで手に取らずに過ごしてきました。
先日アマゾンでKindle配本がセールをしていたので、いい機会と思い数冊まとめて購入しました。
本作品は星の数ほどレビュー記事があるので、ここで詳しく書き記すまでもありません。
ごく簡単に、そして誤解を恐れずに言うならば、青春のある部分を切り取った群像劇であるということです。
この物語から明確ななにかを得ることはないでしょう。
ただ、そこには誰の心にもある「普遍的な風景」が描かれています。
誰もが経験し感じた「あのこと」が、ここに書き記されています。
そこに既視感をおぼえ、なじみ深い自分の体の一部分を改めて知るような、不思議な体験をすることになります。
本作品からなにかを読み取るのではなく、ただ感じるという読書本来のありかたを楽しめます。
さらに、文章のリズムの良さ、言葉選びの美しさといった、読書本来の楽しみ方もできます。
物語の舞台は8月の暑い夏ですが、やはり読むのも夏が似合いそうです。
暇つぶしにぼんやり読むような、さらっとした軽い感触が心地いい。
細かいところですが、登場人物の会話で、ときおり「僕」が返す言葉が好きです。
たとえば、鼠がパイロットになりたかったと話す場面で
「操縦士になりたいと思ったよ、昔ね。でも目を悪くしてあきらめた。」
という言葉に
「そう?」
と返します。
この「そう?」というあいづちって、日本ではあまりないですよね。
この軽い感じがすてきでした。
読んでいて感じたのは、小説というよりも、詩歌に近いような感覚でした。
スピッツのマサムネくんがインタビューでよく語っているのですが、歌詞について
「もちろん歌詞にはいろんな意味が込められているんだけど、それを説明しようっていう気持ちはなくて。聴いた人が感じたとおりに受け取ってくれればいいし、それを聞いて、そういう受け取り方もあるんだなって」
というように、この作品も著者のメッセージを読み取ろうと努力するものではなく、読み手がそれぞれに感じたことが正解なのかなと思います。
「風の歌を聴け」ってタイトルなのに、そんなくだりまったく出てこないし。
スピッツの「ロビンソン」みたいなもんですね。
「ロビンソン」なんか出てこないし、宇宙の風に乗るって言われても宇宙に風吹いてないし。笑
村上さんの作品は読者によって好みが千差万別で、この「風の歌を聴け」が一番好きという人も大変多く見かけますが「初期作品は苦手」という人もあり、「エッセイだけ好き」とか「短編だけ好き」とか、本当にいろいろです。
ちなみに私は彼の本格長編が一番好きです。
ご本人もおっしゃっていますが、やはり長編を書くのがもっとも力のいる作業で、それゆえ読みごたえも格別です。
数年に一度、彼の長編が突然発表されるたびに、人生のもっともわくわくするごほうびのひとつがまたやってきた、と思います。
長編作品のなかでもっとも好きな作品は「1Q84」ですが、最新作の「騎士団長殺し」が僅差で1位の座を競っています(あくまで私ランキングですが)。
彼の作品の魅力はいくつもありますが、特筆すべきはその文章の美しさと、情景がありありと目の前に広がる表現力にあります。
長編作品を読んでいると、いつのまにか主人公の世界を一緒に見ているような、視界が変わる瞬間があります。
彼の言葉を借りるならば「井戸の中へ降りていく」ということです。
その「物語に入り込んだ」状態こそ、読書の醍醐味といえます。
この物語の冒頭で「僕」が語っていること、そこに未来を暗示しているような一文がありました。
「弁解するつもりはない。少くともここに語られていることは現在の僕におけるベストだ。つけ加えることは何もない。それでも僕はこんな風にも考えている。うまくいけばずっと先に、何年か何十年か先に、救済された自分を発見することができるかもしれない、と。そしてその時、象は平原に還り僕はより美しい言葉で世界を語り始めるだろう。」
もちろん、この一文を書いたときの彼は、数十年後の自分を想像すらできなかったはずです。
それなのになぜか未来を言い当てているようなこの一文が、時を超えて私たちの心にさざなみを起こすということが、小さな奇跡のように思えるのです。
村上さんってばもしかして、ドラえもんのタイムマシンでちょっと未来を見てきたんじゃないかしら。