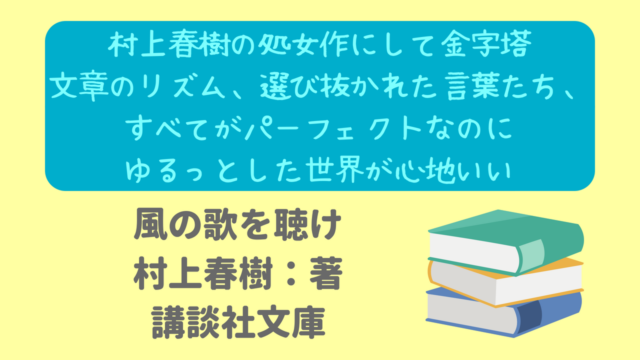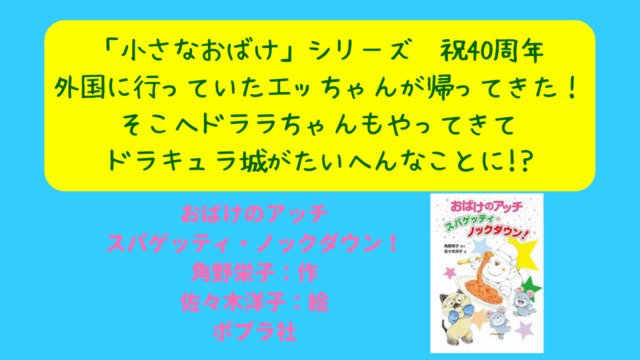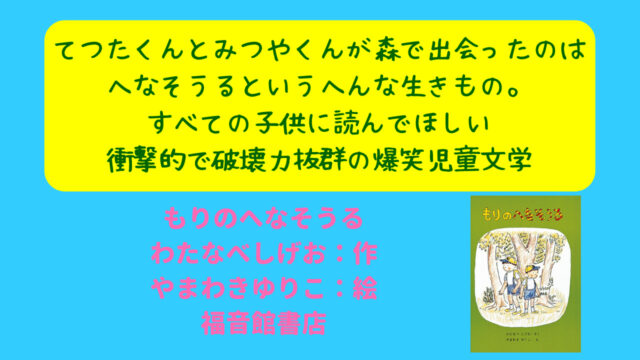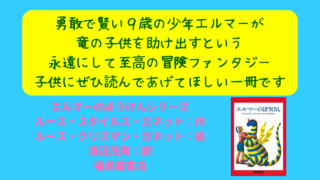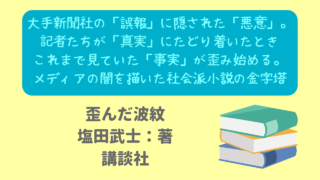吹上奇譚
第一話 ミミとこだち
第二話 どんぶり
第三話 ざしきわらし
よしもとばなな:著
幻冬舎
あらすじ
海と山に囲まれた小さな町、吹上(ふきあげ)には奇妙な現象が起こる。
死体が屍人となり動き回るのだ。
吹上町で生まれ育ったミミには、現実に起きた出来事を夢で知る「夢見」と、屍人を操ることのできる「屍人使い」の能力が備わっていた。
父は自動車事故で帰らぬ人となり、母は事故に遭って以来眠り続けたまま意識が戻らない。
ミミと双子の妹のこだちはそんな町から逃げるように東京へ出て、ふたりでささやかに楽しく暮らしていたが、ある日こだちが「吹上町へ帰る」と言い姿を消してしまう。
行方不明となったこだちを捜すため、ミミもまた吹上町へ戻るが、そこでミミは自分の運命と向き合うことになる。
ニャム評
大好きな、大好きな作家、よしもとばななちゃんの新作書き下ろし作品は、三部構成の連続小説です。
第一話の「ミミとこだち」を読んでまず一番に思ったことは、ついにばななちゃんが全部丸出しの小説を書いた、とうとうここまでやったか、ということでした。
たぶんいままでは「すべての読み手」に配慮し、ある程度の注釈あるいは翻訳の働きをする文章を要所に織り交ぜていたのを、本作でとうとう削除したんだな、ということでした。
例えるとしたら、これまでは「宇宙人から聞いた話」を読み手にわかるように書いていたのを、「じつを言うと自分が宇宙人だったんで、宇宙の話をそのまま書くよ」ということになった、みたいな。
「宇宙人から聞いた話」と「宇宙人が語る話」は似て非なるもので、地球から月を見るのと、月へ実際行くのとでまったく違うというようなことです。
この説明も、わかる人にはわかるでしょうし、わからない人にはまったくわからないだろうと思います。
「魂の本」と、私が勝手に名付けているのですが、ばななちゃんの本は魂を震わせる力を持っていて、読み手はその行間から目には見えない、しかし確実に手で触れるような感触を持ったなにかを受け取ることができます。
残念ながら受け取れない人には、この作品たちの存在意義がわからないかもしれません。
文学とは人間の生存に必須のものではなく、さらに文学のなかでも一部の本には本自身が読み手を選ぶという特性があります。
そして本作は間違いなく「読み手を選ぶ」本であろうと個人的には感じます。
文学は自由であるがゆえに、すべての人にとって開かれた世界でなければならないという制約もありません。
文学の海を泳ぐには自らが泳法を身につける必要があり、その泳法は誰も教えてはくれないため、自分で手足を動かして泳ぐ感覚を習得するしかないのです。
さて、このようにいうと「文学」とは排他的であるように感じますが、もちろんそうではありません。
読書とは、制約と義務によって不自由さに縛られた社会に生きる人間が、自由を得るためのツールであると私は考えています。
とくに現代はインターネット上に散らばった真贋の判別が難しい情報を「いま起きている事実」であると誤認しやすく、声の大きい人が叫ぶ主張を真実であると鵜呑みする人が多くなっていて、そのことを危惧しています。
こんな時代だからこそ、文学が人々の心に必要になっているのだと強く感じるのですが、その理由は「読書は真実にたどり着くための近道」であると思っているからです。
読書という行為は文字を目で追いながら、行間に込められた作者の声に耳を澄ますということです。
ひとつの書物にひとつの真実が隠されており、それを知ることで世界の謎を解く方程式をひとつ得たことになります。
この方程式を積み上げていくことで、世の中の有象無象の出来事を選別し判断する審美眼が培われてゆくのです。
書物は方程式であるとともに、自身を回復する薬効を持つものもあります。
まるで魔法回復薬のようですが、そのように言って差し支えないでしょう。
その効能を持つ書物が文学、純文学と呼ばれる一群の作品であると思っています。
本作を読んで、心の少しだけすり切れた部分、ちょっとほころびたところにしみ込んでいくような、優しさがじわーっと軟膏みたいに効いていくような感じ。
そういう感触を久々に感じました。
やっぱりばななちゃんの物語には膏薬みたいな効能があって、それを感じるアンテナがまだ自分のなかにあることをうれしく思いました。
一時は下北沢とふなっしーのことばかり書いていてどうなることかと思っていたばななちゃんですが、ご自身もおっしゃるとおり30年の間物語を書いてきて、ついにこの世界を書き表すことができるようになったんだなと感じました。
第一話「ミミとこだち」ではとにかく異世界の扉を開けてしまったことに度肝を抜かれましたが、第二話の「どんぶり」ではばななちゃんの持つ「働く人へのいたわり」が全編にわたって綴られているような、優しさと慈愛に満ちたあたたかさを感じました。
すべての働く女の子たちへ、がんばって、あなたはひとりじゃないし、誰にも奪うことのできない宝石のようなきらめきを持っているから、下を向いて悲しまないでいいんだよと、そんなふうに語りかけているような思いやりを感じました。
ばななちゃんの物語はいつだって「働く女の子たち」への応援歌であり、「働く」「女の子」は非常に広義で、ほぼすべての人に当てはまるのですが、自分でも気づかなかった体の不調を「ここが弱ってるよ」と教えてくれるような、ツボをぐいぐい押すような、自分のことをよくわかってくれている整体師みたいな存在です。
そして「どんぶり」が主題であるとおり、処女作の「キッチン」とどこかでつながっているような空気を感じました。
さみしさ、孤独、絶望感、それを「食べること」によって力強く乗り越える力。
やっぱりこの人は食べ物のことを書くのが天才的にうまいなぁ、食べることの力を誰よりも熟知しているなぁとしみじみ思いました。
本作もふせんだらけになりましたが、私がとくに好きだった一文を引用します。
友だちができた、なんてきれいな言葉。地上のいろいろな言葉のなかでもそうとうにいいほうに属するその言葉。
「吹上奇譚 第二話 どんぶり」85ページ
私の大好きなマンガ「CIPHER」の一番好きなシーンでも、同じことが語られています。
主人公のアニス・マーフィという女の子が、同じく主人公のサイファに向かって発するセリフ。
「友だちってのは人間に対する最高の尊称だとおれは思うぜ」
「友だち」は、動物のなかで人間だけが得ることのできる関係性です。
「恋人」や「家族」よりももっと純粋で崇高な思いやりの関係。
だからこそ友だちは得難く、貴重な存在なのです。
ばななちゃんの作品はおすすめしたいけれどわかりやすく説明するのは非常に困難で、書評として正しく伝えられないのがもどかしいです。
ばななちゃんもあとがきで同じように語っています。
やりたい放題やってるな! これこそがほんもののカルトだな! もうだれもついてこれないところまで来ちまったな、と思う。
でもこれが私のほんとうにしたかったことで、するべきだったこと。
わかる人、必要な人には必ず役立つものだ。
184ページ あとがきより
読み終わったあとで、「なんだばななちゃんもそう思ってるのか」と思わず笑いました。
よしもとばななの作品を語ることは「自分の内側」を語ることと同義であり、それは村上春樹作品にも言えることですが、読んだ人それぞれがユニーク(唯一)の感想を持つので、画一的に「こういう物語である」とは語れないんですよね。
おそらく、これまでにばなな作品を通ってきた人なら必ず胸に響く物語です。
そしてばなな作品を読んだことがない人は、びっくりするかもしれないけれど、とにかく既存のフィルターはいったん横に置いて、物語に耳を澄ませてみてほしいです。
あなたが「一所懸命にがんばっている女の子」であれば、きっと物語はあなたになにかを語りかけてくるはずですから。
この作品だけでもいい(私や、私の他の作品を好きでなくてもいい)から、大好きになってくれる人がいたらいいなと思います。
地上を生きること、肉体を持っていること、どれも厳しく苦しい要素の大きなことばかり。だから人はそれぞれの夢を見る。そしてことさらに夢が必要な不器用な人たちがいる。その夢が人生を片すみに追いやるのではなく、人生にとっての魔法の杖となるような。
そんな夢を見るための力を、このおかしな人たちがみなさんに与えてくれますように、つらい夜にそっと寄り添ってくれますように。
185ページ あとがきより